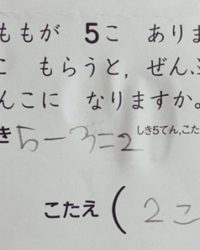戦後日本の英語教育
2016年11月2日 CATEGORY - 日本人と英語

前々回と前回に引き続き、「英語と日本軍」からテーマを取り上げて見たいと思いますが、今回は「戦後日本の英語教育」です。
日本が戦争に負け、GHQの占領を受けることになり、その占領政策の一環として「戦後日本の英語教育」が開始されるのですが、このあたりのことについて本書では詳細されていました。
アメリカは1942年ころからすでに太平洋戦争に勝つことを前提として対日占領政策を準備していました。その中の英語教育に関することに注目すると、「あらゆる学校と大学において英語教育を制度化し、そのための授業時間数を増加させる」という内容が盛り込まれていました。
当初アメリカが念頭に置いていた占領政策は、一歩間違えれば沖縄のように軍制を敷かれる危険をはらむものでした。事実、日本の敗戦後、1945年9月2日にGHQから日本に出された「布告」は「英語を公用語とする」ことを含む恐るべき内容でした。
これに対して日本は、すぐさまマッカーサーに対して交渉をし、土壇場でアメリカを中心とする連合国軍による直接統治は回避されました。これによって、日本の公用語が英語になることが免れたのです。
もし、英語が公用語となっていれば、かつて多くの植民地がそうであったように、英語を使える少数のエリートと、使えない圧倒的な大衆と二国民が分断されていたことだろうと著者は考えています。
一方で、日本側も国際社会の復帰に英語が必要といった理由から、1945年12月14日の国会で「英語奨励に関する請願」を可決承認しました。このころ、ソ連を盟主とする共産陣営とアメリカを盟主とする資本主義陣営に世界が二分され、それぞれの陣営においてロシア語と英語が圧倒的な優勢言語となりつつあり、日本のこの決断は日本の国際社会における方向性にとってとても重要なことでした。
ところが、日本の文部省は新制中学校への外国語(英語)の導入に対しては消極的でした。
なぜなら、旧制の中等学校で英語を学ぶことができたのは、同世代の2~3割程度だったために、すべての中学生に英語を教えるには必要な教師の数が圧倒的に足りなかったからです。
しかしながら、新制中学への外国語の導入は文部省の反対にもかかわらず、既定方針としてすすめられ、新学期に間に合わせるべく文部省著作の新制中学校用英語教科書が大急ぎで刊行されたのです。
こうして1947年4月に新制中学校がスタートし、当時英語を担当した教員の総数は22,611人、このうち英語の免許を持つ有資格教員は2,740人しかおらず、実に9割近くが無免許で英語を教えていたことになります。
私としては、「英語を教える」力と「教員資格」には、ほとんど関連性は少ないと考えており、特にランゲッジ・ヴィレッジにおいては講師の採用の際に、その有無についてまったく考慮しないのですが、この件については少々問題があったのではないかと思います。
なぜなら、その9割の方々は、そのすべてがそうだとは言いませんが、そのうちの少なくない方々が、「英語を教える」ということを前提に教育されておらず、英語についての興味も能力も十分ではないという状態だったところに、急遽、英語の教師としての任をあたえられたと推察されるからです。
これはまさに、小学校英語導入の構図と全く同じだと考えます。(この件についての記事はこちら。)
英語教育についての興味も経験も能力もない人間を急遽、英語教師として速成し、学生に「英語」と「その言葉が使われている国の文化」に触れさせ、国際理解を促すということには明らかな無理があったはずです。
私は今回この事実を本書によって知らされ、次のようなことを考えました。
本来言語というものは「文法」と「会話」が有機的に融合して初めて「コミュニケーション」が成立するはずのものです。ですから、まず「文法」を重点的に教え、それをツールとして頭の中に入れさせます。そのあと、そのツールを使って「会話」につなげるトレーニングを施せば、非常にバランスのとれた英語教育になります。
ですが、後者を行うことは、非常に高い能力が必要となります。それは、「会話」というものは、それを行う人間からどのような内容の文章が飛び出すか予想がつかないので、それに的確な指導を与えるには相当なバリエーションに対応できる能力を教師が持っていることが必要となります。
ですから、上記の通り、速成された講師では、「会話」を諦め、「文法」を中心とした座学に特化して教えていく方針をとらざるを得なかったと考えられます。
スタート時点においてこの方針がとられれば、その教師によって教育された後進の者たちの姿勢もそれに準じたものになるのは当然のことで、日本の英語教育の偏りというものが形成していってしまったのではないかと思いました。
日本の学校英語教育を歴史的観点から見直すという貴重な機会をいただきました。