
言語は双方向性が命
2019年8月9日 CATEGORY - 日本人と英語
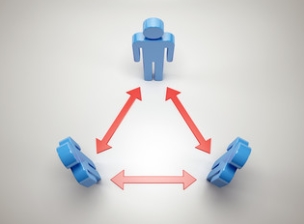
前々回、前回と、書籍紹介ブログにてご紹介した「だから英語は教育なんだ」よりテーマをいただいて、書いていますが、第三回目のテーマは「言語教育と双方向性」についてです。
言語教育を本当に実質的なものにするためには、言語がコミュニケーションツールである以上、「双方向(インターラクティブ)」なものにしなければならないのは当然です。
ランゲッジ・ヴィレッジが、「国内留学」はもちろんのこと、「文法講座」においても学校教育では3年もしくは6年かかっても実現できない「英文法を会話に結びつける」ことを2泊もしくは5泊という短期間で実現できるのは、まさに「双方向性」のメリットを最大限に活用しているからです。
ただし、それはランゲッジ・ヴィレッジの講座がその定員を最大8名に設定するというシステムが前提となっているからであり、そのことを学校教育に求めることができない以上、その二つを比べることはフェアではありません。
ですが、本書には学校教育においても「双方向性」を取りこむことを可能にするアイデアが提示されていましたのでご紹介します。
「今考えると奥住公夫先生との出会いは運命だったように思う。先生の授業を見ていて頭をハンマーで殴られたような大きなショックを受けた。生徒たちが実にイキイキと自己表現をしていたのである。奥住先生は決して生徒を叱らない。むしろ温かく包み込んでいく。生徒への言葉かけ一つとっても、筆者のように否定するような言い方、粗を探すような言い方ではなく、思わず元気ができるような言い方であった。授業を参観しているだけで、教室の中がとても居心地よく感じられた。『自己表現』はこんなにも授業をみずみずしくするのか。今まで遮二無二やってきた授業は一体何だったのだろう。そのころの筆者はテストの平均点を同僚や他の学校の平均と比べて、一喜一憂していた。これでいいのだと思っていた指導法は、解き方のノウハウを教え込もうとするものだった。そこには一人一人の考えや驚きなどは存在しない。しかし、目の前で展開されている授業では、生徒同士が確かに心を通い合わせ、ともに英語を学んでいる。間違えた生徒たちでさえ、楽しそうに笑っているではないか。もっと生徒の目がきらきらするような授業がしたい。教え込むのではなく、生徒たちが自ら意見を言い、それを関わらせて互いに気づきあえるような授業がしたい。筆者の胸は熱くなった。」
それを実現するのが、「ペア学習」でした。
「ペアは最小限のコミュニケーションのユニットである。ペアにすると集団の中に埋もれる生徒がいなくなる。一人一人が主役なのだ。教師は生徒たちが必要感を感じるようなタスクでペア学習を活性化すればよい。ただし、それを実現するためにはそのペアの作り方に気を配らなければならない。クラスを英語の得意なグループとそれ以外のグループの分ける。一人一人に紙を配って、相手のグループの中から一緒にやりたい生徒の名前を四人分書く。教師がそれを集めてマッチングさせるのである。しかし、クラスには誰からも支持されない生徒が一人二人いるものである。そんなときはその生徒が最初に名前を書いている生徒に事前に根回ししておく。ただし、くれぐれも押し付けない。こうしてペアが決まる。だが、これで終わりではない。ペア学習では、ペアで学習するノウハウと技量を生徒の間に根気強く育てなければならない。心地の良いペアを作ることはもちろん大事だが、さらに大事なのは、教師がそのペアをよく観察し、取り組みを評価し、クラス全体にそれを広めていくことである。こうすれば、生徒が見えてくる。」
正直に言えば、この内容を見た時、一クラス8名を最大定員にしているランゲッジ・ヴィレッジの仕組みに慣れてしまっている私からすると非常にまどろっこしい感じをどうしても受けてしまいました。
なぜなら、この8名という最大定員は、教師と生徒とのペアを構成しながらも全体の調和をとりうるぎりぎり人数であるため、このような「ペア学習」では教師対生徒の一対一の構築を諦めることによって、やらなければならないことが多すぎると感じるからです。
ただ、それはランゲッジ・ヴィレッジが相当の報酬をいただくことで恵まれた環境を作ることができるからであって、公教育の範疇で考えれば、このようなタスクは当然にして受け入れなければなりません。
そして、本書の筆者は実際にそれを実行しているわけです。
もう一度繰り返しますが、言語がコミュニケーションツールである以上、言語教育に「双方向性」を取り込むことは絶対に必要なことだと考えます。
また、小学校英語が制度として始まった今、小学校には中学校以上にこのことが求められると考えます。
このようなことは、このように一部の志ある教師が例外的に行うのではなく、学校教育全体で当然に必要なことだと認識し、その運用ノウハウの共有を継続して行っていく必要があると強く思いました。
















