
言語習得の科学
2014年4月27日 CATEGORY - 日本人と英語

この仕事をしていると実に頻繁に次の質問を受けます。
「英語は早期に始めるにこしたことはないですよね?」
これは英語に限らず教育全般について世の多くの親が抱く疑問です。いや、疑問ではなくそのような自分の確信に対して裏付けを得たいという願望かもしれません。
この一般的な親御さんがもつ「確信」の根拠となっている考えがいわゆる「臨界期説」というものです。
しかし、私はこの臨界期説に基づく英語の早期教育に対しては、はっきり反対の立場をとっています。このことについては以前の記事「小学校英語のなにが問題か」にて書きました。
その臨界期説をはじめとする「脳科学」という学問についてより正しい認識を持つことに資する本を見つけましたのでご紹介したいと思います。その本が こちら 東京大学医学部付属病院 小児科医長 榊原洋一著「子どもの脳の発達 臨界期・敏感期」です。
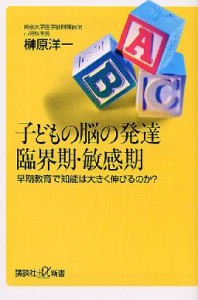
まず、この本を読んで分かることは、臨界期説をはじめとする「脳科学」による研究成果の多くが未だに「仮説」に過ぎないということです。
このことを前提した上で「早期教育」などの議論をしていく必要があるにもかかわらず、世間、とりわけ子を持つ親の間ではこの研究成果が「仮説」ではなく、「事実」という認識の下で理解されてしまっていることがまず大きな問題であるということに気づかされました。
そもそも「脳科学」という学問は実は他の科学と比較して根本的に発展の速度が制限されてしまう学問です。
なぜなら、科学は実験の積み重ねで発達していくものですが、脳、特に人間の脳に対して直接的に実験を行うことは倫理上許されないことだからです。そして、万物の霊長である人間の脳とその他の動物の脳では、他の臓器とは比べ物にならないくらいの大きな隔たりがあるわけで、動物実験での結果を人間に置き換えて理解することはかなりの頻度で無意味となります。
ですから、この仮説をもとに子供の教育を云々すること自体について熟慮する必要があると思います。このように整理をした上で「臨界期説」を以下に見てみます。
「臨界期説」の根拠としてあげられるサンプルとしては次の二つが有名です。
「ガチョウの刷り込み(インプリンティング)」と「オオカミ少女カマラとアマラ」です。
一つ目のインプリンティングは、ガチョウが孵化した後、5時間~24時間の間に初めて見たものを「母親」と認識して常にそれを追いかけるという性質のことです。そして、これは「孵化後5時間~24時間」に限定され、それを超えるとインプリンティングは成立しない、だから「臨界」期というわけです。
このインプリンティングの発見はその後の動物行動学の発展だけでなく、人間の乳児の発達の研究にも大きく貢献したことは事実です。しかし、鳥類であるガチョウの性質を人間に当てはめて、特に言語の習得には、この時期に学習の機会を与えないと言語習得が不可能となってしまう「臨界期」があるはずだとするほど万物の霊長人間は単純ではないと著者はいいます。
二つ目のオオカミ少女の話は、1920年にインドのカルカッタで狼が住んでいた洞窟で発見された八歳と一歳半の二人の少女をキリスト教の宣教師が引き取って育てたというものです。二人は、夜になると遠吠えし、四足で早く走れ、鶏を見ると飛びかかり、生のままで食べてしまったといわれています。そして、妹のアマラは早死にし、姉のカマラは17歳まで生きましたが、結局数十の言葉しか覚えることができなかったようです。
このことをもって、人間の学習にも臨界期があって、その時期に何を習得するかで「狼」にもなるし「人間」にもなってしまうというように、インプリンティングの合わせて臨界期説の有力な根拠として機能しています。
しかし、著者はこの二人の少女は狼に育てられたのではなく、極端なネグレクト(育児放棄)の犠牲者だったのではないかと医学的見地から推測されています。二人は、幼少時からまともな世話をされず、身体的虐待から逃れるため家から逃げ出し、たまたま狼が住みかとしていた洞窟の中にいたところを保護された可能性がある。そして、四足で早く走れたというのは解剖学上無理な話で、話を面白おかしくするための誇張であるはずで、鶏を生でという話も極度の飢えのための行動だったというものです。
ただ、姉のカマラが17歳まで生きたのに「結局数十の言葉しか覚えることができなかった」という事実は、少なくとも思考の基礎の獲得である母国語の習得については、ここまで極端な言語的隔離を行った場合には考慮の必要はあるかもしれないと思います。
著者は、この二つの例から一つの結論を導きだすことは非常に危険なことであると言います。そして、実験が積み重ねられていない以上、そのように推測することは科学の世界では当然のことだと思います。
「科学の世界では」そうですが、一般論として、科学者ではない私がこの話だけを聞いて乱暴な結論付けをするとすれば、以下のようなものになると思います。
「自らの思考の基となる母国語の獲得」に関してはいわゆる臨界期の「ようなもの」は存在する。しかし、一旦思考の基礎を身に着けたあとに行われる外国語の習得などの学習については、人間の高度な脳の機能についてはいまだほとんど分かっていない以上、言及するに及ばない。
つまり、仮説はどこまでいっても仮説で、なおかつ人間への応用はほとんど未知だということを私たちは理解すべきです。
このことから、この脳科学についての「仮説」を「事実」のようにして教育業界のマーケティングに利用することは今の段階ではあってはならないことだと思います。
このことは教育業界に限らず、先日のブログ記事、「物事の本質をとらえる力」でも書いたように、すべての業界において、情報を発信する事業者側、受け取る消費者側双方が本質を考えることを徹底する必要があると思います。
















