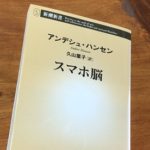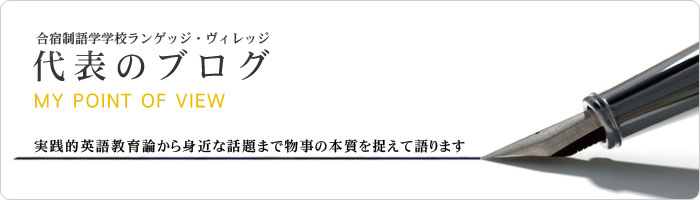
合理的なのに愚かな戦略
2016年4月10日 CATEGORY - 代表ブログ
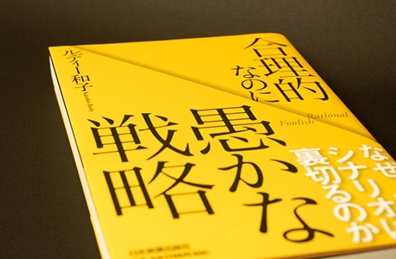
皆さん、こんにちは。
数少ない経営学者として私が尊敬する方に一橋大学の楠木建という教授がいらっしゃいます。
すでにこのブログで何回も紹介しております。
私が楠木教授を尊敬する大きな理由として以下のような彼の経営学者の仕事の定義があります。
「経営は、論理が2割で気合が8割で、その2割の枠内で論理をじっくり考え実務家の人々に提供すること」
もし、論理が10だったら学習さえすれば誰でも経営できてしまうわけです。だからと言って、割合として2はあるわけだから全くの無駄ではない。そこに、経営学の限定的な意味があるという主張です。
この「経営は、論理が2割で気合が8割」という事実について、具体的な事例をあげながら説明している本を自分の積読の中から見つけて読んでみました。
その名も「合理的なのに愚かな戦略」という本です。
気合の部分が8割存在するということは、論理的(合理的)であっても結果的に愚かな結論に行きついてしまう可能性が十分にあるということであり、だからそこ経営は難しいということになります。
本書は、そのあたりのところを非常に分かりやすく書かれている良書でした。 例えば、「イノベーションのジレンマ」という現象の説明がありました。これは、「競争の感覚を研ぎ澄まし、顧客の意見に注意深く耳を傾け、新技術に積極的に投資し、それでもなお、市場での優位を失う優良企業の話」です。
これはこういうことです。
「実績のある優秀な企業は、新しいイノベーションの存在に気づいても、既存市場の顧客の要求に応え、既存製品の性能の改善を続けたほうが、財務的に魅力があるという理由から(これはこれで至極合理的な判断)イノベーションを無視してしまう。また、新しい技術に投資をしても、十分なだけの結果が出ないと判断して継続的な投資をしない。顧客の要求に従うことがチャンスを逃すことになる。」
ソニーなどが、顧客の様々な要求に真剣に耳を傾け、高機能な音楽プレーヤーを開発し続けているうちに、音楽はいつの間にか携帯電話の中に入るものになっていたというようなことです。
これを、裏付ける実際の経営者の言葉には次のようなものがあります。
「顧客は製品を見せるまでは、自分たちが何を欲しているか分からない。」(スティーブ・ジョブズ)
「もし、顧客に何が欲しいかと聞いていたら、もっと速く走る馬と答えているだろう。」(ヘンリー・フォード)
これらのジレンマを克服するには、「論理」ではなく「感情」、もしくは「勇気」というものが必要となります。
上記の顧客に耳を傾けることを否定したり、そもそも顧客の想像の限界を見切っているという姿勢は、その時点で論理ではなく、自らの信念の問題です。
しつこいようですが、ここの部分がまさに「経営は、論理が2割で気合が8割」の言わんとしているところなのかもしれません。企業の方向性が論理の上に乗っていればいるほど、いつの間にか違う方向に行ってしまうのをどのように制御するのか。
スティーブジョブズやヘンリーフォードという特殊な人間だけがその制御をできるのか。それとも、「気合」「感情」「勇気」によって、組織としても継続的に制御することができるのか。
それは、アップルのような、かつて破壊的イノベーションをもたらした結果、自らが「優良企業」となった者が、彼らにもいずれ訪れるそのジレンマにどう対処するのかを待って見る必要がありそうです。