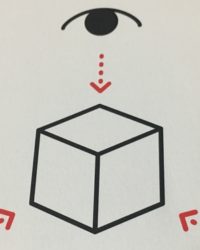日本の英語学100年の歴史
2014年9月3日 CATEGORY - 日本人と英語

以前の書籍紹介で上記「わが国の英語学100年」について紹介しました。その中で私は、「私には『英語学』という学問が本書を読んでも具体的なイメージが浮かぶまでに至らなかった」と正直に告白しています。(笑)
しかし、そうではあっても少なくとも英語に関わる仕事をしている以上、この学問の概略およびその歴史の流れをほんのさわりだけでも理解しておくことには一定の価値があるのではないかと考え直し、本ブログの記事に本書の概略をまとめてみようと思い立ちました。
まず、初めにそもそも「英語学」とは何かを明らかにします。以下ウィキペディアより
「英語学とは、英語を客観的に記述する学問のことである。すなわち、無意識的に話している(すでに知っている)英語にどんな規則や構造があるのかを解明し、理論的に説明するのが目的である。よって、意識的に学ばなければいけない児童・生徒・学生を対象とした規範的な英語教育の質向上のための学問ではない。」
つまり、英語の仕組みを科学的に説明する学問ということになると思います。
最初に日本に来た英国人は1600年のウィリアム・アダムズ(日本名:三浦按針)ですが、日本において英語の研究が始まったのは1808年のフェートン号事件(オランダとの交易しか認められなかった長崎においてイギリス船フェートン号がオランダ船と偽って入港し、幕府に対し食料や薪炭を脅迫により要求した事件)以降です。
ただ、幕末から明治にかけての英語研究は実学、つまり英語学習そのもの止まりでした。
科学的英語学は1912年9/20に刊行の市河三喜氏の「英文法研究」(研究社)から始まったと言われています。市河氏は、本書の趣旨として以下のように述べています。
「言語現象をありのままに受け入れ、それがそうである理由を英語そのものの歴史に照らしたり他の言語と比較したり、心理学的立場から説明をしようとするもの」
大正から昭和に入り英語学の発展は本格化します。その中で中心的に活躍するのがその後東大の教授となる市河氏とその門下生らです。
彼らは、海外文献の翻訳、英語辞典の編纂、英語学関連雑誌への論文出稿等の活動によって広く一般の英語学とに影響を与えることになります。1941年から始まる太平洋戦争にいたっても英語学は一時停滞しますが、幸い中断はされませんでした。
戦後は、アメリカの影響を強く受けることにより、アメリカ英語やアメリカ構造言語学へ配慮して20世紀中ごろまでの欧米における英文法研究の成果の集大成として、大塚高信、岩崎民平、中島文雄(市河氏の弟子)氏らにより全26巻にわたる<英文法シリーズ>や大塚氏による<新英文法辞典>などが刊行されます。
これらは、改定を重ね今なお日本の英語英文学界に広く受け入れられています。
1940~50年代にかけて多くの若手研究者のアメリカ留学が実現したこともあって、アメリカ構造言語学が日本の英語学に強い影響を与えることになります。この構造言語学とは、言語を記号的体系と考え、あらゆる言語に普遍的な最小の記号単位の数や組み合わせによって各言語の差を作るとするものです。
この考え方は人間の行動をすべて刺激とそれへの反応が一般化したものと捉え、直接観察可能でない心的現象行動についても観察可能な行動に還元する傾向にあったことがあげられる。要するにすべての言語における差異を無理やり科学的にこじつけて理解しようという学問的姿勢です。
やはりその無理がたたって、60年代になってくると構造言語学は行き詰まってきます。そして、言語の本質の解明を目指す生成文法にとってかわられることになります。
この生成文法とは、アメリカの言語哲学者チョムスキーによって1950年代に提案された文法理論で、人間はみなその母語に関わらず普遍的文法を生まれながらに備えていると仮定してその探求を目指す学問です。この考え方に従えば、さまざまな言語を獲得するということは生得的な初期状態である「普遍文法」から個別言語への遷移と理解され、生成文法は、自然言語であればどのような個別言語の状態への遷移可能ということです。
日本においてこれらを主導したのが、太田朗、荒木一雄、安井稔氏ら文献学(フィロロジー)の素養に立って理論研究を推進した方々です。
1980年ころからは、高度な言語知識、言語直感を必要とする最近の理論研究において、日本の研究者が日本語の研究あるいは日英の対象研究に向かっていきます。これらの動きは、古典主義から離れ、日本人が日本から英語を見る研究に移行しているということだと言えると思います。
以上が、日本における英語学の歴史100年の流れです。
このように見てみると、日本における「英語学」は、まずは実践的英語教育方法の模索から始まり、だんだんと言語の普遍的性質の探求につながっていっていることが分かります。そして、この流れの最後のほうではこの分野が専門的に非常に細かく分かれ行きます。書籍紹介ブログの記事にて指摘しましたが、本書の著者は、昨今の研究者の小粒化、超専門化について痛烈に警鐘を鳴らされています。
ただ、この学問の歴史の流れを真剣に追ってみると、その細分化の度合いは非常に高く、これらの心理学的もしくは脳科学的な分野にまで手を出さなければならないような学問にまで成長していることがよく分かります。
その上で、「古英語、中英語、シェイクスピアなど初期近代英語を代表する作家たちの著作さえ研究者に読まれることがなくなってきてしまった」というような批判については理解はできますが、一方でそこまで求めては可哀想かもしれないという気持ちにも正直なりました。(笑)