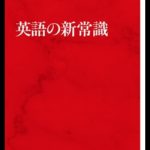グローバル社会は英語基準社会
2018年6月10日 CATEGORY - 日本人と英語
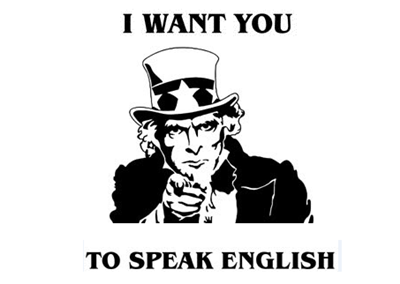
前々回、前回と「英語だけの外国語教育は失敗する」よりいくつかテーマをいただいて書いていますが、今回取り上げますのは、斎藤兆史先生による「グローバル社会における能力評価」についてです。
極論すれば、「英語ができる愚者」と「英語ができない賢人」のどちらが評価されるべきなのかという話です。
著者は次のような指摘をしています。
「モノリンガルの英語話者が日本人の知的能力を英語力で判定していると思しき事例を何度も見聞きしたことがあります。同僚の英語話者の教師たちが、あの学生はできる、昔教えた時にとてもよくできたから教員として採用すべきだ、と言って彼らが名をあげるのは、例外なく英語ができる人たちです。しかしながら、私たちから見ると母語による研究能力がもっと高い学生はいくらでもいます。英語による会議が増えてモノリンガルの英語話者教員の発言力が高まり、学生評価や人事の基準として英語力が重視されるようになると必然的に日本の大学の研究・教育力は低下します。皮肉なことですが、英語を勉強すればするほど、そのような言語の力学がよく見えてきます。」
このことが社会の前面に出た例が、欧米の旧植民地での人材評価だと思います。
その国の人間のすべての能力評価が英語というフィルターをかけた上でなされてしまうのです。
これは、宗主国と植民地という力でねじ伏せられた関係において起こるのであればまだあきらめがつくかもしれません。
しかし、現代の日本においてグローバル化が意識しすぎることは、そのような関係をむしろ積極的に日本の側から欲するということに等しいのではないかと思えてきます。
欧米のメディアによる国際大学ランキングに翻弄されている日本の大学を見ていると、彼らが抱える学生の本質的な能力を、単なるコミュニケーションツールにすぎない英語の運用能力という本質的ではない枠に落とし込まざるを得ないという悲劇を見せつけられる気がします。
この一点だけをとっても、日本の進むべき道はグローバル化ではなく、国際化(複言語主義)であるということを確信せざるを得ません。