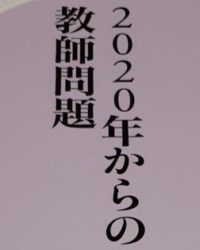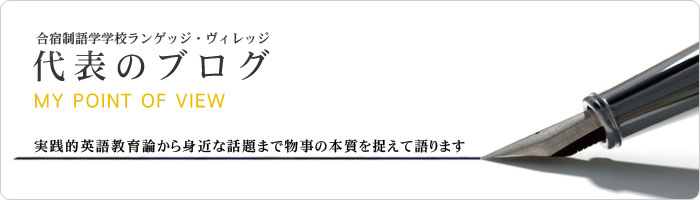
イオンを創った女
2019年5月17日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。
少し前のプレジデントオンラインの記事でに、ユニクロの柳井会長が「今まで読んだ人事の本の中で最高の本」と絶賛されていた本を読みました。
タイトルの通り「イオンを創った女」という本です。
この本は、現在のイオン社長の岡田元也氏の父卓也氏の実姉にあたる小嶋千鶴子氏の評伝です。
彼女は、戦前・戦中そして戦後と卓也氏が大学を出て経営者となるまで、岡田屋という家業をまもり、ジャスコという企業に変貌させ、それをイオン(GMS)という産業にまで成長させる礎を作った人です。
私の感想を書く前に、この記事の柳井会長の感想を引用しておきます。
「これを読むと、やはり小嶋さんがイオンの実質的な創業者だなとよくわかります。小嶋さんは小売業の経営者を超えていますね。小嶋さんは実に見識が広い。その広い見識をもとに、教育者であり、クリエイティブディレクターでもあり、組織をまとめることもする。それこそ真の経営者なんだと思います。」
私が、本書を読んで印象的だったことが二つあります。
一つは、彼女の「学問」と「実業」のバランス感覚の素晴らしさでした。それは以下のエピソードから強く感じたものです。
「戦争が終わった1945年12月、40坪の店の棟上げ式をした。ただ、材木が不足していたのであちらこちら探し回ってやっとの思いでかき集め、翌年の3月には開店した。この年はインフレによる新円切り替えが行われたが、その前に千鶴子は会社に残っていたお金のすべてを商品に変えた。第一次世界大戦後のドイツでスーパーインフレが起こりお金に値打ちがなくなったことを本により学んで知っていただからである。」
私も本が好きですので、新しい知識に触れることの喜びを知っているつもりです。ですが同時に、本好きは、本が好きだからこそその喜び自体に満足しがちだということも知っています。
なかなか、そこで得た「学問」を「実業」に生かすということにスムーズにつなげることは非常に難しいことだと思います。
もし、「知識」に触れる喜びを知っている本好きが、その知識を実業にスムーズにつなげることができるのであれば、決して日本のバブル崩壊やアメリカのリーマンショックなどは起こらなかったはずですし、起こったとしてもその後の混乱はあそこまで拡大しなかったはずです。
これが、「学者は経営ができない」という悪口につながるのだと思いますが、学者でなくても、多くの経営者も、なかなか知識欲があったとしても、そのバランスをとることは難しいのです。
その意味で、彼女のこのエピソードは非常に印象的でした。
また、もう一つは、世代交代の妙です。
「小嶋は1977年、60歳にしてジャスコの役員を退任した。以前から役員の定年を60歳と決めていた小嶋はあっさりと未練なく実行した。このことは役員がいつまでも役員として会社に残ることの前例を作らないという意味を含んでいる。身をもって先例を作ったのだ。若い人たちへのバトンタッチを促す意味である。いつの世も若者の過ちよりももっと害のあるものは『老人の跋扈である』と小嶋は考えていた。」
冒頭で紹介したユニクロの柳井会長は、実はイオン(ジャスコ)の出身であり、彼の成功は小島千鶴子氏が育てたこのイオンという企業で働いたという経験と無関係ではないのかもしれないと強く思いました。
後は、彼女が示した世代交代の巧みさをユニクロでどのように実現されるか、この点を本からでなく実践から勉強させていただきたいなと思っています。