
祖国とは国語である
2018年8月24日 CATEGORY - 代表ブログ
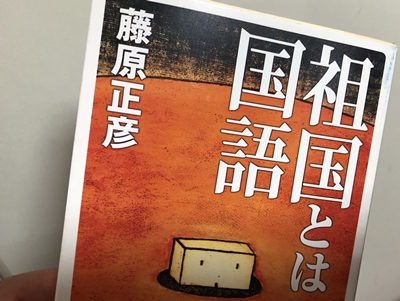
皆さん、こんにちは。
先日、「日本人と英語」ブログにて日本人にとっての国語の大切さについて、かなりの熱を込めて力説してしまいましたが、そのことをもう少し深めて考えてみたいと思い、一冊の本を手にしました。
それは、あの誰もが知っている「国家の品格」というベストセラー(いまだ私は読んでいませんが)を書かれた数学者藤原正彦氏による著作「祖国とは国語」です。
本書のタイトル「祖国とは国語」という言葉、このままでは意味がよく分かりません。
日本語では「よく分かりません」で済むかもしれませんが、英語で My home country is my mother tongue. と言えば完全に文章として論理破綻です。
この言葉は、もともとルーマニア人の思想家、エミール・シオランの
On n’habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c’est cela et rien d’autre.
(人は、国に住むのではない。国語に住むのだ。『国語』こそが、我々の『祖国』だ。 )
というフランス語によってモチベートされたタイトルだと思われますが、祖国を祖国たらしめる文化・伝統・情緒などの大部分が国語の中に包含されていることを意味しています。
著者は、ユダヤ民族が長い苦難の歴史を経ても20世紀に国家の再建が可能となった一方で、同じように苦難の歴史を経ても言語を奪われてしまった琉球やアイヌの民族が国家として立ち上がることができていない理由がここにあると言います。
そして、彼らは長い歴史の中で常に(人は、国に住むのではない。国語に住むのだ。『国語』こそが、我々の『祖国』だ。 )ということを意識することで、自らの国語であるヘブライ語を守り続けたのです。
このグローバル社会において、イスラエルはITの世界でその存在感を増しています。
その存在感を世界に示す中ではちろん、英語をコミュニケーションツールとして活用していますが、ヘブライ語が英語に取って代わられてしまう可能性などみじんも感じていないはずです。
それは、自らの存在感、力の源が自らの民族の文化・伝統・情緒などの大部分が凝縮されている自らの国語であるヘブライ語であることを理解しているからだと思います。
一方で、日本では自らの存在感、力の源であるはずの日本語を軽視する流れが色濃くなっています。
小学校において国語の時間を減らして英語を導入する教育政策はその大きな証拠となっています。この件に関して本書に書かれたエピソードに愕然としました。
「平成14年に導入された新カリキュラムでは小学校国語の総時間数は戦前の1/3ほどである。理由の一つは多くの人が国語を情報伝達の道具としてしか考えないことになる。2002年から新カリキュラムに英語が入ると聞いた私は、『国語は大幅に減らされますが大丈夫ですか?』と英語導入を推進する教育学者に尋ねると彼は待ってましたとばかりに『英語以外の科目はすべて日本語で教えますから心配無用です。』と答えた。」
この姿勢は、この変革以前のカリキュラムで学習した私の時代にも程度の差はあれど感じられたものです。
「受験において国語ではどうせ差は出ないのだから、受験テクニックとしてはその時間を国語以外の教科に充てるのが正解です。」
こんなアドバイスを国語の教師自身から聞かされることなどざらでした。
そうではありません。
日本人にとっての国語である日本語は、「情報伝達の道具」以上の存在であり、民族の文化・伝統・情緒などの大部分が凝縮されている思考の基礎および知恵の源泉である。
これを民族として意識してその教育のために何が必要なのかを考えることの重要性を本書から改めて知らされた気がします。
















