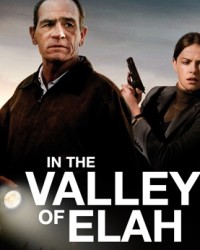「多様性」の本質とは何にか
2025年7月13日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。
本日(2025年7月13日)の読売新聞朝刊の「あれから」に、1994年の東京大学の入試で「史上三人目の全盲の東大生」として同紙に取り上げられた星加良司さんが、あれから31年の歳月を経て、東京大学においてキャリアを積み上げ教授となって「多様性を認め合う社会をどう作っていくか」という課題に取り組む中での現在の思いを語る記事がありました。
その星加教授の「多様性」対する見方が本当に鋭く深く、その本質に迫っているものでしたのでその部分を引用するのが今回の趣旨ではあるのですが、その鋭さ深さを感じるためには、星加教授の来し方を知らなければ不可能だと思いますので、まずはそちらを要約引用します(といっても詳しくお伝えしたいので少々長くなってしまいますがご了承ください)。
「瀬戸内海を望む愛媛県新居浜市で生まれた。星加さんは1歳で小児がんを患い、治療のため東京の大病院へ通い、入退院を繰り返した。最初は左目、次第に右目の視力も失われ、5歳で全盲になった。物心がついてからは見えないことが当たり前。だから強い喪失感や絶望感を覚えた記憶はない。ただ、幼心に感じていたのは、『見えないことそのものよりも、見えないことで生き方の選択肢を限定されることへの違和感』だ。愛媛県内にある県立盲学校は、自宅から約60キロ離れた松山市に1校のみで親元を離れて寄宿生活をするしか選択肢がない時代だった。両親も手元で育てたいと望み、何より自分が友達と同じ学校へ行きたいと地元の市立小学校に通う『例外中の例外』を選んだ。特別扱いはしない。入学した小学校は、良くも悪くもそれが受け入れ条件だった。目が見える子と平等に扱う。必要な配慮はするが、日々の安全確保も教材の準備も、まずは親が責任をもって引き受けることが求められた。息子が安全に登下校及び学習ができるように母・澄子さんは全力でサポートした。朝、集団登校の輪にまじって息子と一緒に学校へ向かい、空き教室で待機した。最大の役割は、教科書やドリル、プリントに書かれた文章を点字にすること。息子とともに点字を学びながら、専用の機械を使い、家や教室で点訳するのが日課となった。『みんなと一緒に勉強したい』という息子の意思は揺るがなかった。テストの時は、書いた線が立体的に盛り上がる特殊な用紙にひらがなや漢字を書き、正しく書けているか指で触って確かめてから解答を提出した。点字で答えるより時間も労力もかかったが、点字がわからない先生に内容を理解してもらうには、これしか選択肢がなかった。ドッジボールでは鈴の入ったボールを転がして遊び、短距離走では、前を走る友達の『良司!』と叫ぶ声を頼りに駆け抜けた。組み体操や登山、ブラスバンドにも挑戦し、テストはたいて1番をとった。特別扱いはしないという学校の方針のおかげか、星加さんは殊更、障害を意識することなく成長した。東京の大学に進むことを明確に意識したのは、中学3年の時だ。目が見えない代わりに聴覚に優れ、英語の発音は完璧。その才能にほれ込んだ担任で英語の先生に勧められ、高松宮杯全日本中学校英語弁論大会に出場すると、見事優勝を果たした。高校は、地元の進学校へ進んだ。ここでも『選択肢』は多くはなく、家でおとなしく勉強するしかなかったが、いつの間にか成績が伸び、ついには東大の文科三類に合格する。」
このような経験を経てきた彼が、現在の研究対象である「障害学」へと導かれるきっかけとなった「多様性の本質」を語る言葉との出会いは以下のものでした。
「『逆境に打ち勝って立派になった障害者』として持ち上げられながら始まった大学時代において私はそうした世間の見方とそれに応えようとしている自分に嫌気がさしていて、『障害』を研究分野にすることを意図的に避けた。もやもやした思いを抱えたまま進んだ東大大学院でのある学問との出会いが、その後の生き方を決定づけた。本で知った『障害学』はこんなことを説いていた。例えば、人間の大半が目の見えない人で、目の見える人が少数派だったらどうだろう。部屋は一日中暗く、全部が点字で表現されるから、少数派は生活しづらい。つまり、目が見えないから不便なのではなく、社会が目の見える多数派のためにしか作られていないから不便なのだ、と。何かが頭にガツーンと落ちてきた。これまでの人生は全盲というだけで、あらゆる局面で生き方の選択肢が制限されてきた。しかも、何かを頑張るだけで、『障害者なのにすごいね』と称賛される。障害学の考え方が、幼いころから自分が抱えてきた小さな違和感や疑問の数々とつながった。障害を研究するのではなく、生涯を通じて社会を研究する。『これは自分の学問だ』と確信した。」
私は最近、「多様性」という言葉が、人々の「対立」や「分断」のきっかけにすらなっているのではないかと思うことがしばしばでしたが、それは私たちがこの星加教授が示してくれた「多様性の本質」を理解できない状態で「多様性」の議論をしてきたからではないか、という思いを強くしました。
この数年で最も優れた読売新聞の記事だったと思います。