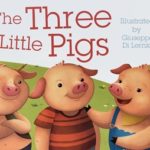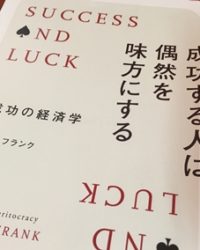ネイティブが最良の教師とは限らない
2018年1月14日 CATEGORY - 日本人と英語

英語関連書籍ではありませんが、以前にご紹介した落合陽一氏の「これからの世界をつくる仲間たちへ」という本の中に、当たり前ですがしかし、英語を学習する上で重要な考え方が書かれていましたのでご紹介します。
それは、「ネイティブが最良の教師とは限らない」というものです。
本書において著者は、「デジタルネイティブ」という概念について詳しく説明されています。
「デジタルネイティブ」とは生まれながらにしてデジタルカルチャーを当たり前のものとして享受している人間のことです。
幼稚園のころからyoutubeの検索機能を見よう見まねでやってのけてしまううちの7歳の子供たちは、ワープロに大学生になって初めて触れた私には、まさにこのデジタルネイティブそのものに映ります。
彼らは、デジタルが当たり前でなかった時の状況がどんなものだったかを知りません。
ですから、デジタルの技術がなかった時代には、何ができなかったのかを直感的に理解できないため、逆にこれから20年後、30年後にはどのような変化がもたらされるのかについて想像できないはずです。
つまり、デジタルネイティブは、自分自身をデジタルとの関係において客観視できないため、そこで解決すべき問題が何なのかも見えてこないということです。
これと同じことが、言語的に英語ネイティブにも言えるはずだということが今回の私の主張です。
とは言え、ランゲッジ・ヴィレッジの国内留学に関わる講師は基本的にすべてネイティブスピーカーです。
そのネイティブ講師に対してランゲッジ・ヴィレッジが期待していることは、日本語を全く介さずに生活する環境の「一部」としてそこに存在し続けることです。
彼らは、その環境の一部になって、日本人の受講者に対して英語を発するための動機付けを圧倒的長時間にわたって行うことができるようにトレーニングされています。
私には、いくら可愛くても、5歳児との会話を一日中続けることは絶対にできません。しかし、ランゲッジ・ヴィレッジの外国人講師たちはそれと同等のことを毎日毎日やってくれているということになります。
つまり、彼らに必要なことは言語教育に関する専門知識ではなく、言語的に不完全な相手といくらでも会話を継続するコミュニケーションの胆力だということが分かります。
決して彼らに英語の文法の構造的な説明を期待しているわけではないので、彼らの採用の時に「言語学」の素養については一切査定の対象とはしていないのです。
それらの能力は、英語を外国語として学び、その構造を客観的にに整理をしてきた私たち日本人講師にこそ期待されていることですし、そのとおり彼らネイティブに英語の「構造分析力」で負けるはずはないのです。
しかし、まだまだこのあたりのことをきっちりと整理されておらず、何でもかんでもネイティブでないと、と考えて研修を企画するケースが目立ちますので注意が必要です。
今回は、まったく関係ないと思われるコンピューターの話から、「ネイティブ」の素養についての話になりました。