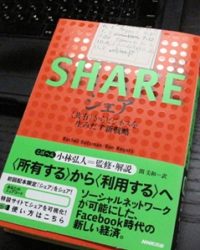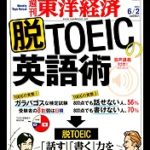翻訳本の読みにくさ
2017年3月24日 CATEGORY - 日本人と英語
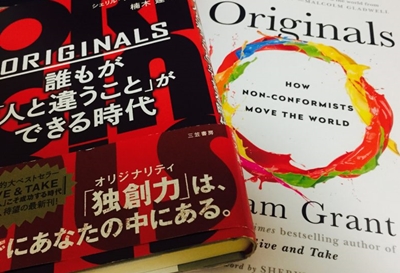
以前に書籍紹介ブログにてご紹介した「日本語の論理」より、いくつかのトピックを抜粋して、日本語と英語の関係について、以後何回かにわたって考えていきたいと思います。
まず、第一回目の今回は、翻訳本の違和感の原因について。
私は以前のブログ記事で何度か、「翻訳本を読むのが苦手」だと公言しています。
どんなに優秀な翻訳者が翻訳したとしても、どうしても、流れがしっくりこないからです。
この本で著者はその違和感の原因を二つあげています。
一つ目は、その翻訳の仕方があまりに「形式的でありすぎること」です。
これは、翻訳が単語や成句に訳語を与えて、語順を日本語風に変えるところまでやるけれども、それは文章の中だけで、文章の順序については変えることをしないということから生じています。
日本語と西洋の言語との言語的距離を考えれば、語順だけでなく、文章の順番も適宜変更しなければ日本語らしくならないのに、語順を変えるだけで翻訳完了としてしまうという片手落ちの翻訳が行われているのです。
この結果生まれた翻訳文は日本語離れしたものになります。
まさにこれこそが、私が感じていた「しっくりこない」感だと思いました。
そして二つ目は、著者以外でもよく主張されるようですが、西洋の言語が名詞中心の構造を持っているのに対して、日本語は動詞中心の構造をもっていることから、まず最初に翻訳されて出来上がる日本語がどうしても、西洋の言語の構造を持たざるを得ず、それを日本語の構造に変換する努力を惜しみがちだということです。
これは、次のような例を見ると分かりやすいです。
「The recognition of this fact contributes to the solution of this matter.」
という英語の文章を英語の構造のままに日本語にすると、
「この事実の認識が問題の解決に貢献する。」
となります。
これ一文だけですと、そこまで違和感がないかもしれませんが、このような名詞中心の文章が続いていくと、その違和感はかなりのものとなると思います。
これに対して、日本語の動詞中心の構造に変換する努力を付け加えると、
「これが分かれば問題はずっと解決しやすくなる。」
どうでしょうか。
これが、まさに「しっくりくる」日本語だと思います。
この点は、私がかねてよりずっと感じていた違和感を非常に的確に解消してくれるものでした。
私にとっては、この問題はずっと引っかかっていたものだったので、この読書体験はもはや「感動」といったレベルのものでした。
こういった素晴らしい本との偶然の出会いというものも、読書の大きな楽しみの一つだと思います。