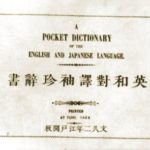people & persons
2024年5月13日 CATEGORY - 日本人と英語

書籍紹介ブログにてご紹介した「英語の種あかし」からテーマをいただいて書いていますが、第四回目のテーマは「people(人々)」と「persons(人たち)」です。
明確な理由は分からないけれどなんとなく「使い難い」と思われる単語として「person」の複数形の「persons」が挙げられます。
なぜ「使い難い」と感じていたのかといえば、本書にも書かれている通り、「person」の複数形は「people」だと学校で習った記憶があるからだということしか言えません。
なぜなら、そう習ったときも「personsは存在しない」ということを併せて教えてもらっていたわけではないからです。
このように、教える側が自らの理解の不十分さをおして、ただ状況証拠的を並べただけのような提示をしてしまうのであれば、教わる側がそうならざるを得ないのも無理はないことですが、このケースに限らず英語の教授の現場ではこのようなことは結構頻発します。(例えば「過去形と現在完了形の違い」)
ただ本書にはこの部分から逃げずに理解を深めさせようとする意識が感じされられる部分がありましたので以下引用します。
「昔、学校で英語を習ったとき、私などは、person(人)の複数形はpeopleであると教えられたのだが、最近はpersonの複数形としてpersonsも結構普通に見かけるようになった。もともとpersonsも間違いではなく、法律用語や文語としては昔から使われている。
Ted Kennedy gave Kerry his own chief staff and one of his gifted campaign persons.(テッド・ケネディはケリーに自分のスタッフのチーフと才能ある選挙運動員の一人を与えた。)
また別のところではこんな文章も見かけた。
Obese persons are subject to tremendous discrimination inmost countries.(肥満した人間は多くの国で甚だしい差別を受けやすい。)
私も、英語を書くときはまだしも、話すときにはついpersonsと言ってしまうことがあるので、こんな風にpersonsが幅を利かせるようになってくれるのは大変好ましいことだと思っている。しかし、考えてみると日本語でも、『人』を複数でいうときには、『人々』というときと、『人たち』というときがある。人間のやること、考えることは、どこでもそれほど違ってはいないのかもしれない。」
この説明の中の一つ目の「one of his gifted campaign persons」については、「法律用語」的な性質を帯びているとも捉えられますが、二つ目の「Obese persons」については明らかに法律用語でも文語でもありませんので、一般的に「persons」の使用が認められつつあるというのは事実のようです。
そもそも、学校で習った「『person』の複数形は『people』だ」ということ自体、peopleが「集合名詞」という特殊な名詞に分類されていることから、疑ってかかるべきではないかと思います。
とはいえ、最も大事な「persons」が幅を利かせるようになってきた理由については、本書をもってしても明らかにされていませんでした。
これについては、あくまでも私個人意見にすぎませんが、最近男女同権の意識の高まりによって「fireman」や「policeman」などを「fireperson」や「policeperson」と呼ぶことが当たり前になってきたこともあって、それらの複数形としての「firepersons」や「policepersons」が頻繁に使われるようになってきたことから、単純な「person」の複数形としての「persons」への抵抗も同様に少なくなってきたというのが理由の一つではないかと考えますがいかがでしょうか。
これも「言葉は生き物だ」と捉えればその可能性も十分にあるように思います。