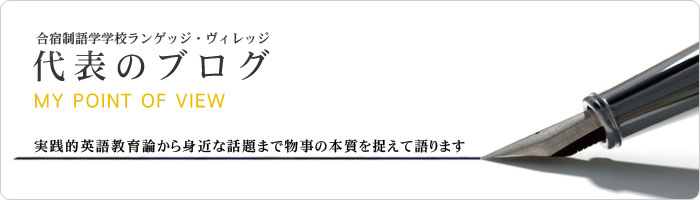
双子、三つ子の研究 その3
2015年10月23日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。 前々回、前回と「ふたごと教育」に関して、特に「双生児による研究」によって導き出される人間一般の遺伝と環境についての考察を見てきました。
今回は、「双生児の研究」を継続的に行っている本書の監修者である「東京大学教育学部付属中等教育学校」による「ふたご、みつご」自体の考察について見ていきたいと思います。
世界的に見ても、双生児に関する研究というのは、基本的には「双生児による研究」であり、「双生児の研究」という「ふたご」や「三つ子」の特性に目を向けた研究はほとんど見られないようです。
そのことからすると、「東京大学教育学部付属中等教育学校」は、世界的にも珍しい存在であり、ここでの経験の蓄積は、「双生児の研究」にとって、非常に重要な意味を持っていると思われます。
特に、中学高校の6年間という長期にわたり、ごく普通の教育活動を通して「ふたご」「三つ子」を見守り続けているこの学校の先生方の知見は、私たち「ふたご」「三つ子」を持つ親の立場からすると非常に興味深いものです。
以下に、その「ふたご」「三つ子」との関わりを通じて、先生方が感じた「遺伝」と「環境」の関係性についての意見を引用します。
「自分とは何者か、という問いの答えは、決して遺伝によって決められるものではありません。他者との出会いや自らの積み重ねてきた経験として、その中で培われてきた問題意識や価値観といったものが自らを作り上げ、個性として結実してくるのです。つまり、『ふたご』であることの『遺伝的近さ』は自分を構成する数ある要素の掛け算のうちの一要素に過ぎないと言えます。だからこそ、そこに教育の可能性が存在していると言えるのです。」
前回のブログで私は、研究結果によるデータをそのまま受け入れると、私たちが行っている「教育」という活動の影響力は思っていたよりもずっと、限定的なものに思えてしまうような気がすると書きましたが、「東京大学教育学部付属中等教育学校」の先生方の知見は、それらの研究結果によるデータを見事に覆す性格のものでした。
では、なぜそのようなデータと実際に、「ふたご」「三つ子」と間近に接している人間の感覚とでずれが生じるのでしょうか?
その点についても、本書には記述がありましたので引用します。
「(それは、データをとる前提自体の不完全性を排除できないからです。例えば、)基本的にこれらの研究データは中流以上の家庭を対象としてとられたものです。例えば、経済的、身体的にハイリスクな環境下で生育した者の遺伝率は極めて低くなるとのデータがあるため、導き出された遺伝率等の数値は絶対的なものではないと思われます。(一部加筆修正)」
本書でのこのような指摘は、昨今のデータ至上主義に対してのアンチテーゼであると思われます。また、人間の多様性をデータに完全に反映させることの難しさを改めて私たちに教えてくれるものだと思います。
このような考えの差は、「ふたご」「三つ子」を単なる研究対象としてみている研究者と「ふたご」「三つ子」に対して、それぞれ「個」もった存在として接している先生方との感覚のずれそのものを表しているようにも感じました。
そして、本書における「東京大学教育学部付属中等教育学校」の先生方の知見は、「教育の可能性」を信じる理由を私たちに強く与えてくれるものだと感じました。
















