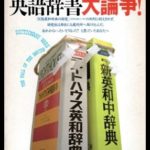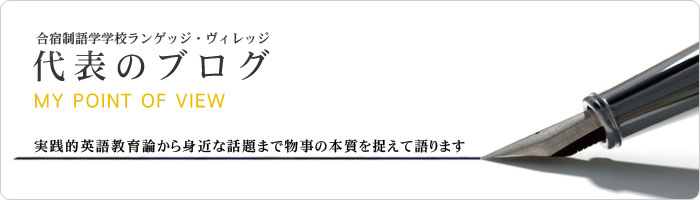
ブルシットジョブの何が問題か
2022年1月30日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。
前回の記事に引き続き、「ブルシットジョブ」について考えてみたいと思います。
今回は、「ブルシットジョブ」のどこが問題かという命題についてです。
前回、ケインズの予言は一般的には「外れた」と思われているが、実は当たっていたと考えるべきではないかという話を取り上げました。
つまり、現代人は実際にはかつてより半分以下しか働かなくても十分に生活することができるようになっているが、「ブルシットジョブ」を作り出し、本来しなくてもよい仕事をすることで、働いているふりをしているからだと。
そうであるならば、「ブルシットジョブ」をしている現代人は労働しなければ生きていけなかったかつての人たちよりも「幸せ」であるはずだということになります。
にもかかわらず、鬱病をはじめとする精神疾患に悩まされる人の数は圧倒的に現代の方が多いのはなぜなのでしょうか。
この疑問に対して著者は次のような回答をしています。
それは、「ブルシットジョブ」によって人間の根源的な喜びの源泉である「世界に変化を与える原因になること」が失われるから。
ドイツの心理学者カール・グロースは、「幼児が自分が予測できる影響を世界に与えられることに初めて気づいた時にものすごく喜ぶ」という現象を発見しました。
それはほんの小さなこと、例えば自分が腕を振り回すと鉛筆が転がるとか、毛玉を転がすことで母親が驚くことなど、自分がそういう状況を作り出すことで、他者(物)に影響を及ぼすことに対して大いに喜びを感じるということです。
これはつまり人間にとっては「(自分が世の中の変化の)原因になること」が根源的な「喜び」につながるということの発見です。
このことを前提にすると、自らの仕事が「ブルシットジョブ」であると自覚するということはすなわち、この根源的な喜びの喪失を意味し、「自己存立の危機」につながると理解することができます。
かつての労働者は、今よりもずっと不便で大変な世の中だったけれど、自分の労働がその不便な世の中を少しだけでも良くする「原因」になっていると実感することができた。
一方、そのころに比べ圧倒的に便利で楽な世の中になったけれど、現代の労働者は自分の労働がその世の中を少しもよくする「原因」になっている実感を得ることができない。
なるほど、精神疾患に悩まされる人の数は圧倒的に現代の方が多いのは自明です。
前回に引き続き、常に自分の仕事がそうならないような仕事への向き合い方をしていたいと思います。