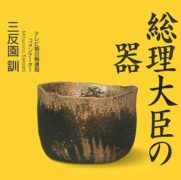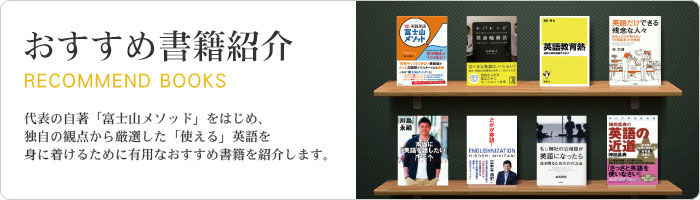
日本人と英語 もうひとつの英語百年史 #86
2014年11月16日 CATEGORY - おすすめ書籍紹介
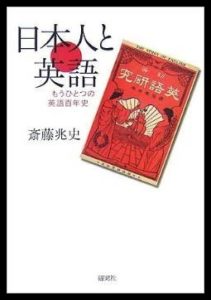
【書籍名】 日本人と英語 もうひとつの英語百年史
【著者】 齋藤兆史
【出版社】 研究社
【価格】 ¥2,000 + 税
【購入】 こちら
「五十年史」には生き証人がいるが「百年史」にはそれがいない。
100年という期間はこのようにとてつもなく長い期間なのですが、その時間の中で我々日本人は英語とどのようにかかわってきたのかを概観しようというのが本書の目的です。
この中で一番印象に残ったのは、日本人と英語の関係が、百年史の当初から今まで、まったく変わっていない点と大きく変わってしまったという点があるという事実でした。
1900年代初頭、日英同盟の締結と日露戦争の勝利の勢いもあって、日本国内では英語関連の雑誌や出版社の設立ラッシュが起こったり、英語学校が大繁盛したりの空前の英語ブームが巻き起こりました。斎藤秀三郎が作った正則英語学校などは最盛期には生徒数が5000人を超え、大繁盛したそうです。
これなどは、現在の英語ブームに引けを取らない日本人の英語好きを物語っており、当時と現在でまったく変わっていない点です。
しかし、学校教育を司る教育行政の動きは大きく変わっています。
というのも、このような英語ブームの中で当時の文部省は英語教育強化に乗り出すどころか、むしろそれに逆行するかのように以下のような訓令を発したと言います。
「英語は元来学習に困難な教科であるから学力に余裕のあるもの、または語学の才能のあるものはいいけれども、世の流行にのってこれを学習するようなものは深く戒めるべき」
困難な英語教育の中でも一番困難で重要な部分である「文法」と「語彙」を軽視して、オーラル重視の名のもとに「九官鳥英語」を小学校から推し進めようとするような本質を踏み外した世論迎合の現在の文部科学省の動きとの差に驚かされました。
世論に迎合することがあってはならない教育という分野において、専門家としての行政が、率先して本質から逸脱してしまっているのを見ると、何のために教育委員会のような政治から独立させる独自の仕組みを設けたのか、非常に大きな疑問とショックを感じることとなりました。
文責:代表 秋山昌広