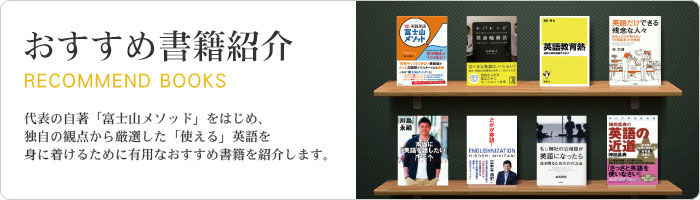
週刊東洋経済 2024年1/20号 #311
2024年3月7日 CATEGORY - おすすめ書籍紹介
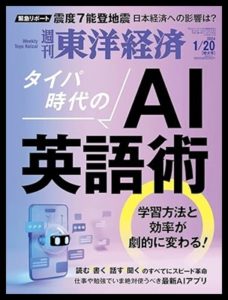
【書籍名】 週刊東洋経済 2024年1/20号
【出版社】 東洋経済新報社
【価格】 ¥773+ 税
【購入】 こちら
「ChatGPTをはじめとしたインタラクティブなやり取りが可能なAIの登場で英語教育に大きな影響が出る。」
と言われはじめてからそれなりの時間が流れ、確かに私自身もGoogle翻訳をかなり頻繁に利用するようになりました。
とはいえ、ChatGPTのすごさを理解しつつもそれを具体的に英語学習や業務の助けに利用する気にはなれず、スマホ相手に英会話のトレーニングをしたりするどころか、それらを具体的に指南する書籍も手に取ることさえありませんでした。
という意味では、本誌は私にとって初めての「それらを具体的に指南する書籍」ということになりました。
本誌の中で東進ハイスクールの安河内哲也先生が「英語学習にパラダイムシフトが起きた。勉強したい人はもう手放せなくなるだろう」と言っているのですが、あながち言い過ぎでもないかもしれません。
というのも、本誌記事が実況中継的に臨場感をもって解説していたこともあって、ようやく重い腰をあげ自分のスマホで体験してそのことを実感するに至ったからです。
以下に、この「パラダイムシフト」についてその安河内先生ともう一人立命館大学教授の山中司先生が見解を述べられていましたので、二人の見解をChatGPT的にまとめてみます。
「このようなパラダイムシフトが起こってしまったのだから教師や試験の役割も変わってしまったと考えるべきです。ただ読み書きを教えるだけの先生は不要で、それに代わって求められるのは生徒のモチベーションを維持し精神的な支えになる役割です。また、試験は自身の英語力を確認するための指標として今後も必要となるかと思いますが、ただその点数によって皆が皆、一喜一憂するような絶対的なものではなく、健康診断のような役割になると思われます。」
ChatGPT以前であっても「ただ読み書きを教えるだけ(=教科書をなぞるだけ)の先生は不要」だったはずですが、今後は「だましがきかなくなる」という意味でそのような先生が一掃されることを望みます。
また、試験に関してもまさにその通りだと思います、、、が、健康診断の結果に毎年一喜一憂(というか全憂)している僕としてはこの件については発言権はないかもしれません。(笑)
















