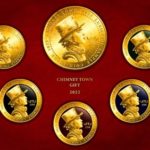なぜ北欧の人々は英語上手なのか
2015年4月1日 CATEGORY - 日本人と英語

先日、「英語を学べばバカになる グローバル思考という妄想」をご紹介しましたが、その中で北欧の国の人々が英語が上手な理由について言及していたので今回はそのことについて考えてみたいと思います。
まず、著者は世界広しと言えども一般市民が自国語以外の英語を話せるというのは例外的な事例に過ぎないと言います。
そして、その例外の一つは、英語を母語とする国の植民地となっていた国だと指摘します。例えば、フィリピンとかシンガポールとかです。このあたりの話は、かつての記事「フィリピンと英語、日本と英語」で詳しくしていますのでご参照ください。
そして、もうひとつの例外として、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドなど北欧の国々を挙げています。
これらの国々に共通していることとして言えるのは、まず人口の少なさです。ノルウェーやフィンランドは人口500万人程度と日本の福岡県程度の規模しかありません。スウェーデンでさえ、900万人程度で大阪府程度。
このような規模の国々では、自国語だけでは経済的にやってはいけません。例えば、出版物ひとつとってもその国の言葉で出版してもとても採算が取れないわけです。それは、映画やテレビ、ラジオなどすべてに言えることです。
基本的にミリオンセラーが存在し得ないのです。
このような状況では、ディズニーアニメを子どもに楽しませようと思ったり、将来、高等教育を受けさせようと思ったら、小さい頃から当たり前のように英語を学ぶことになるのです。
ですから、そこにはものすごく強烈な「必要性」が介在しているということになります。
本書の主張の大部分が、自国語ではない英語がその国で力を持ってしまうということは、英語による支配それはすなわちアメリカの力による支配を受けているということで本来忌み嫌うべき状況だというものでした。
私はその考えはかなりバランスを欠いたものであると思いますが、少なくとも国民国家としての結束という意味ではマイナスに働くことは確かだとは思います。英語を話せる人と話せない人が厳然として存在してしまうような状況になると、国民がバラバラになってしまうからです。
だからこそ、これらの国々では、強力な国家主導体制の下、すべての国民に英語を学ばせることを徹底したというのです。つまり、国家の統合を維持するために、敵陣奥深くにはいりこんで、自らの目的を達成するという「虎穴に入らずんば虎子を得ず」作戦をとったということです。
次に、共通しているのは、その多くが立憲君主国、すなわち王様の国であるというとです。(フィンランドだけは共和国。)
これについても、上記の様に自国語では国家の統合を維持できないため、王室という象徴をいただくことによって何とかして求心力を維持することで国家の統合を維持していると考えるべきだといいます。
これらの指摘は、非常に分かりやすいものだと思いました。
以前の記事の「英語の歴史」でも見たように、今までは、単純に北欧の言葉が、英語に近いから北欧の人が英語上手なのは当たり前のことではないかという理解をしていましたが、それならば、ドイツやフランスなども同じことではないかという疑問には答えられません。
やはりここでも、本質は、「必要性」に基づく「環境」なのだと認識させられました。