
日本人の論理構造
2016年8月7日 CATEGORY - 日本人と英語
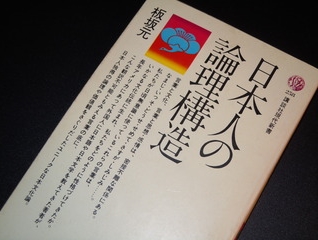
先日、「日本人の論理構造」を書籍紹介ブログにてご紹介しました。
本書は、いくつかの「日本語」を取り上げて日本語の底を流れる日本人の論理や心理を探るというものです。
今回は、本書にて紹介されている例を三つほど取り上げて、我々日本人の精神の特殊性を自覚することで、英語という日本語とは大きく異なる論理を持つ言語を学ぶにあたってのヒントとなればと思っています。
まず一つ目の言葉は、「いっそ」です。
「あれにしようか、これにしようか、それともいっそのこと、こっちにしようか」というように、この言葉は、モノの選択にあたり、それまでの予算など条件の枠を飛び越えた、それまでの比較検討の成果とは無関係な選択がなされるときに使用されます。
このような飛躍的なものごとの決定の仕方は、欧米人から見ると非常に不思議に見えるようです。
なぜなら、欧米人であれば、「急に」飛躍するようなことではなく、普段から言語をフルに活用して、議論を戦わせたうえである結論を導き出されるのが普通だからです。
しかし、日本人のそれは、「急に」なされたものではなく、長い間潜在的にその言葉を発する人の心の中に不満が蓄積され、ある時点で「急に」表面にあらわれるものであって、全体の雰囲気によってそうなることは相手方もある程度は理解できる心の動きだと言えます。
太平洋戦争の前から、真珠湾に至るアメリカと日本のやり取りはまさにそのような違いを物語っていると言えます。
続いて二つ目の言葉は、「せめて」です。
「現実にはお金も仕事もないが、せめて夢の中でだけは贅沢をしたい」というように、この言葉は、現実の厳しさとしては、どうにもこうにもならない状態の中でも、当事者としてみれば感傷的価値とでもいうべきものをせめて守り抜くことで心の平安を求める姿勢の表れだと言えます。
これについては、「わび・さび」という日本文化の良い面として世界的に評価されている美的感覚に近いものがありますが、これらについても実は、日本人の生活が代々実につつましく、いやもっと直接的に言えば貧乏だったことによって仕方がなく作り出されたものだと著者は考えているようです。
この考えについては、反論される人も多いかもしれませんが、私はなんとなく理解ができるような気がします。
というのも、建築にしても、食事にしても、確かに日本のものの良さというものを世界は一定の評価はしてくれますが、決して世界の主流になることはありません。
日本においてすら、建築、食事、音楽などほとんどの分野における主流は欧米のものになってしまっているということをまずは認めなければならないと思います。
三つ目の言葉は、「~られる」です。
「臓器内部にいくつかの腫瘍が認められる」というような、いわゆる「自発」という意味を表現する言葉です。
これなどは、考えてみれば、本当に不思議な表現です。
なぜなら、「腫瘍を認める」のは、ほかでもないその発言者その人なのにもかかわらず、あたかも、客観的に「そのように思える」とするような事前に逃げ道を用意しておくような表現です。
そもそも、欧米の言語には、「自発」という表現は存在せず、日本語を学ぶ欧米人が大いに困る文法テーマのようです。
これなどは、明らかに責任回避の意図が感じられるものです。
明らかに、その判断をしたのは、話者その人に他ならないにもかかわらず、あたかも、社会全体の流れを考えると、その判断を下すことが自然であって、私でなくてもそのような判断が下されたはずですよねという予防線を張っているがごとくです。
ここでは、三つのみを取り上げましたが、ここで見ただけでも日本語、そしてそれを母国語とする日本人の論理というものが非常に独特なものだということが分かりました。
英語を外国語として学ぶにあたっては、この違いをあらかじめ意識しながら進めるのとそうでないのとでは、その結果に大きな差が生じるのは当たり前の話だと思います。
次回は、その学習にあたっての具体的な困難性を一つ取り上げてみたいと思います。
















