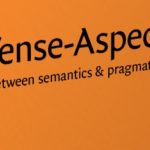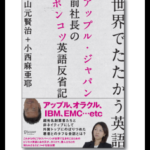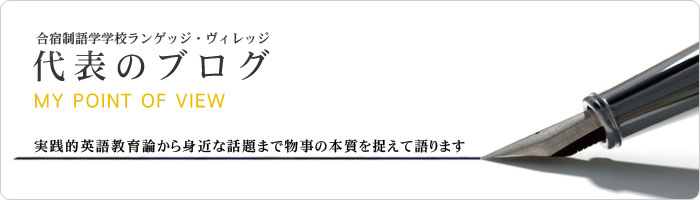
グローバル化とは何か
2018年8月8日 CATEGORY - 代表ブログ
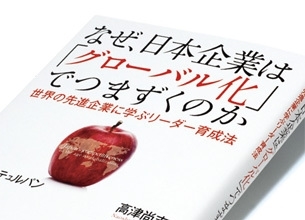
皆さん、こんにちは。
先日、「なぜ、日本企業は『グローバル化』でつまずくのか」という本を、英語学習関連本ではないにもかかわらず「おススメ書籍紹介ブログ」にてご紹介しました。
この本には、それほど多くの英語学習者にとって重要な情報が載っていました。
その重要な情報とは、そもそも「グローバル化」するために必要な要素とは一体何なのかということです。
日本では、一般的に「グローバル化」と言えば、英語をコミュニケーションツールとしながら、ビジネスの仕組みをいかに欧米の仕組みに合わせられるかということに意識が向いていると思います。
場合によっては、グローバル化=英語化という認識しか持たない企業もあるかもしれません。
ですが、本書を読むことで、少なくとも英語によるコミュニケーションはグローバル化の基礎中の基礎、すなわち最も基本的な要素でしかないことが分かります。
つまり、できて当たり前の要素に過ぎないということです。
本書では、グローバル化に必要な重要なキーワードとして、「グローバルマインドセット」という言葉が多用されています。
このグローバルマインドセットとは、3つの能力を軸としたグローバルに活躍するための思考のことです。
そして、3つの能力とは ①認知管理力 ②関係構築力 ③自己管理力です。
この中の②と③については、その名前からもその能力の意味合いを推測することができますし、ローカルな企業活動にとっても当然必要なものでもあるため、必然的に①認知管理力がグローバルに活躍するための特定の要素と考えられますので、こちらを本書より引用します。
「認知管理力とは、自分にとって新しく曖昧な情報を知覚し、判断し、自分の中で意味づける力のことです。それは、高い好奇心を持つということでもあり、認知の歪みや偏りにとらわれないということでもあります。誰しも分からないことはそれだけ不安であり、判断のつかない情報ほど受け入れがたいものです。しかし、異国、異文化ではそういう情報に触れることが極めて多くなります。人によっては自国の文化がすべてで、自国がすべての面で最高だと考えがちですが、他の国や文化に関心を示すことが認知管理力の基本で、異文化理解、異文化コミュニケーションの根本にある能力です。(一部加筆修正)」
そして、この能力は以下の5つの要素から評価されます。
(1)判断を保留する力
何らかの状況や特定の個人に対して性急に否定的な判断を下さず、敢えて判断を差し控えたり、一旦保留したりしようとする能力
(2)問いを立てる力
これまでとは異なる体験を、新たな学びや変化、多様な価値観を取り入れる機会ととらえられる能力
(3)曖昧さへの寛容さ
不確実で曖昧な状況、何が起こっているのかが明確に分からない状況においても動じない能力
(4)コスモポリタン(地球市民)的感性
世界で今起こっている出来事に対して興味と好奇心を持てる能力
(5)関心事への柔軟さ
新しい興味や楽しみを求め続け、慣れないことでも試みようとする意志を持つ能力
この定義をしっかりと読み解けば、やはり以前の記事にて取り上げました、「グローバル化と国際化」という二つの日本語の意味の違いをきちんと整理した上での「国際化」の意味合いが、本当の意味での「グローバル化」を指しているのだということが分かります。
グローバル人材は、意識的に①認知管理力 ②関係構築力 ③自己管理力を鍛えることでなりえるものだということを再度確認すべきです。
英語を母国語としている欧米人が生まれながらの「グローバル人材」ではありません。もし、彼らが日本人よりもグローバルに活躍しているのであれば、それはこれら3つの能力を意識的に鍛えているのだと知るべきです。
日本人にとっては、その第一歩が英語を学ぶということかもしれません。