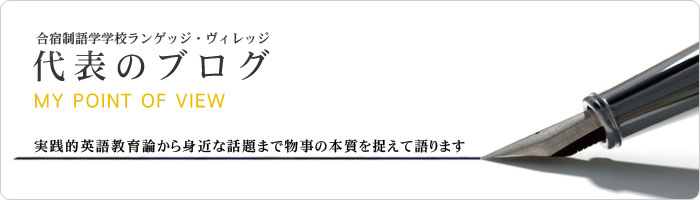
働き方5.0
2020年7月2日 CATEGORY - 代表ブログ
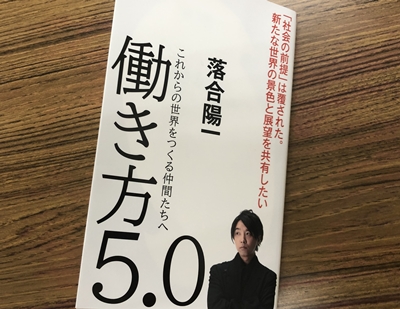
皆さん、こんにちは。
以前の記事にて「10年後に食える仕事、食えない仕事」という書籍をご紹介して、これからの人間は常に、今やっている仕事がAIにもできないか、もしくはAIの方が合理的にできないかと自問自答を繰り返す行動様式を身に着けるべきだと書きました。
そして、その自問自答とは、「人間にしかできない仕事」とは何かを探すことであるとも言い換えられると思うのですが、その書籍にはその具体的な「探し方」については明確に書かれているとは言えないような気がしました。
そのため、その「探し方」についてできるだけ具体的に書かれたものを探した結果、落合陽一氏の「働き方5.0」という書籍を見つけましたのでご紹介したいと思います。
実は本書は、4年前にご紹介した「これからの世界をつくる仲間たちへ」という本をアップデートしたものです。
たった4年前に書かれたものの単なる焼き直しかとも一瞬思いましたが、実際に読んでみるとAIの分野における4年というのは、その当時の常識が全く通用しないとは言わないまでも、かなり大きなアップデートを必要とするくらいの期間であることはよく分かりました。
本書の中で著者は、その探し方として次のようなことを言っています。
「たくさんの異なる常識を自分の中に持つこと、複数のオピニオンリーダーの考え方を並列に持ちながら、自分の人生と比較し、どれとも違った結論に着地できないか、並行して複数のプランを常に考えること」
つまり、「新奇性」と「オリジナリティ」を見つけるために頭脳を使い続ける姿勢を身に着けることが重要だということのようです。
なぜなら、それ以外のことは全てコンピューターの方が確実にスピードと正確性で上回っていることは明らかで勝負にならないからです。
システムにはなくて人間だけにあるものとは「モチベーション」、すなわち「これがやりたい」という動機であり、これだけはどれだけコンピューターが発達してもおそらく唯一人間に適わない部分でしょう。
逆に言えば、この動機をもって働くことができない人間は、確実に「システムに使われる」ことにならざるを得ないというわけです。
しかも、どの時代でも動機をもって仕事をし、その結果「オリジナル」を作ることができる人間の数は非常に限定されているので、今までのように「中流層」を形成していた「中途半端にできる人」の活躍の場が全くなくなってしまうと著者は見ています。
つまり、未来の私たちの社会は「ごく少数の『クリエイティブな人間』と大多数の『コンピューターの下請人間』の二種類の人間による社会」となるというのです。
このように聞くと、なんともひどい社会が来てしまうと思いがちですが、著者の本書における主張は、「だからクリエティブな人間を目指そう」というものと、もう一つは「でもコンピューターの下請人間は必ずしも不幸ではない」というものです。
というのも、来る「AI社会」においてもすべての仕事をAIが行うことができるわけではありません。
なぜなら、「10年後に食える仕事、食えない仕事」で見たように、実働部分を担う「ブルーカラーの仕事」は必要であり続けるからです。
必要なくなるのは、従来その「ブルーカラーの仕事」をマネジメントしていた「ホワイトカラーの仕事」です。
別の見方をすれば、仕事の本質的な価値は、従来もこれからも「ブルーカラーの仕事」が生み出していて、「ホワイトカラーの仕事」はそれを搾取していたとも考えられます。
その「ホワイトカラーの仕事」が電気代だけでそのマネジメントをやってくれるAIに取って代わられるおかげで、多くの人間がAIの下請けになろうとも、直接的に価値の創出を担う「ブルーカラーの仕事」の価値は上がるというわけです。
とはいっても、著者の本書における一番の主張は、モチベーションを持った「クリエイティブな人間」になることが最も幸せな人間の生き方であるというところにあります。
本ブログの目的は「人間にしかできない仕事」の「探し方」でしたので、記事の最後に著者の言うそれを見つけるために意識すべき5つの自問自答を書いておきます。
① その仕事によって誰がハッピーになるのか
② なぜ今その仕事が必要なのか
③(突然思いついたものではなく)過去から続く何を受け継いでいるのか
④ どこで可能なのか(起業してやれるのか大企業でやれるのか)
⑤(自分以外の人が簡単にまねできるのか)参入障壁は十分にあるか
















