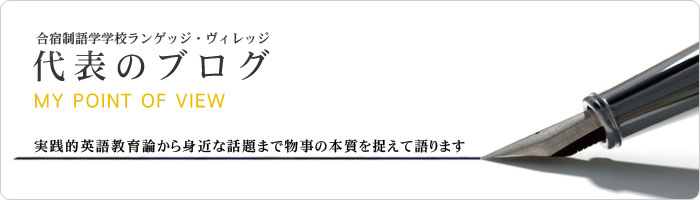
死ぬほど読書
2017年10月18日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。
伊藤忠商事の社長、会長を歴任し、民主党政権において史上初めて民間出身として駐中大使を務めた丹羽宇一郎氏は財界きっての読書好きで知られていますが、その丹羽氏が最近「死ぬほど読書」という読書の意義について書かれた書籍を読みました。
なぜ人間は、読書をすべきなのか。
このことについては、実に様々な人がいろいろな視点から答えてくれていますが、本書で著者が答えている内容は、非常にストンと腹落ちするものでした。
「人間には動物の血と理性の血の両方が流れています。ですが、動物の血は、300万年前にサルから猿人に、70万年前に猿人から原人に、10万年前に原人から現生人類に進化しながら受け継がれた長い歴史を持つものです。それに対して、理性の血は、それに比べてたった5000年前から始まった文明人類としての歴史しか持たないものです。この時間の尺度で見れば、理性の血よりも動物の血のほうが圧倒的に濃く、強いに決まっています。この濃くて強い動物の血を理性の血をもってコントロールするためには、心に栄養をできるだけ与えることしかないのです。(一部加筆修正)」
著者は「この心に栄養を与える」ための方法として読書が最も有用だと考えているのです。
ただ、著者は単に読書がすべてを解決するとは言っていません。
読書をするときには、ただ読むだけではなく、そこで得た情報に対して「考える」作業を経ることによってはじめて「知識」になると言います。
また、もっと言えば、ただ頭の中で「考える」だけではなく、実際の体験、特に責任を伴う仕事を通しての体験を伴うことで、深く考えることを通じて深い「知識」とする必要があると言います。
なぜなら、この世の問題のほぼすべてが「人間との関係」をもとにしているからです。
「問題は人との関係であり、一人で解決するものでもない。他人への想像力と共感が解決へ導いてくれる。問題がある限り、また、それを解決する答えも必ずどこかにある。」
このような問題に直面するということを「体験」というわけですが、その時点で自分の中に「情報」が何もなければ、まったく解決につながりません。
その時のために、「情報」を最も効率的、効果的に自分の中に吸収しておく方法が読書であるわけで、人生をよりよく生きるために読書をしないという選択肢は非常にもったいない。
逆に「情報」だけを読書によって吸収するだけで、それを体験とすり合わせることを一切放棄してしまうことも解決にならないこともまた真なりですが。
このことを、著者は私たちに対して、「このことに気が付かないなんて、本当にもったいないよ。」と教えてくれています。
















