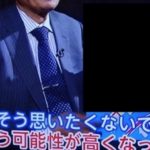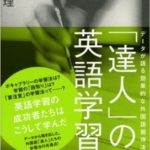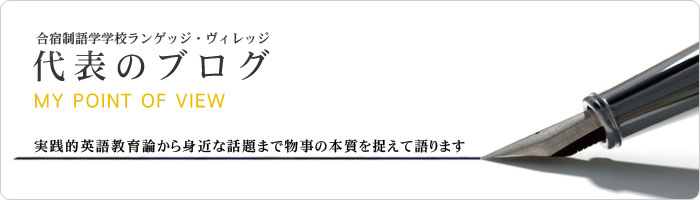
日本の教育の未来への提言
2016年12月25日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。
先日(2016年12月21日)、文部科学大臣の諮問機関「中央教育審議会」が、小中高校の2020年度以降の教育内容を決める次期学習指導要領の基本方針を提示したという記事が、新聞各紙で報道されました。
その目玉は二つあります。
一つは、「小学校5年生からの英語の教科化(3年生からの外国語活動の実施)へのスムーズな移行について」、もう一つは、「高等学校における日本史と世界史を融合した『歴史総合』の創設について」です。
一つ目の「小学校5年生からの英語の教科化へのスムーズな移行について」は、もともとこのブログで何度も取り上げていたことですが、今回の答申では、それを2018年度から先行実施できるように準備すべきだとしたことです。
具体的には、18.19年度を移行期間とし、17年度末までに教材開発や教員研修を進めるように求めました。
2020年にやることが決まっているのであれば、その準備としては当然のことかと思いますし、この件の是非については、私は今まで何度も言及してきましたのでここでは控えます。
今回、詳しく取り上げたいのは二つ目の「高等学校における日本史と世界史を融合した『歴史総合』の創設について」です。
高校の次期学習指導要領が実施される2022年から、近現代に限定した「世界史」と「日本史」を融合した「歴史総合」という科目を始めるようです。
私は中学・高校時代、社会科が一番好きな教科でしたが、不満な点が二つありました。
一つは、「日本史」と「世界史」を分けるという考え方です。これによって、「世界史だけを学ぶ」という日本人としてアンバランスな状態となる可能性があること。
そして、もう一つは、中学にしても高校にしても、原始時代から進めていくことで、最終的に近現代まで行きつかず、もっとも興味を持ちやすい部分をないがしろにされることが多かったことです。
ですので、今回提示された方向性に対しては大賛成、むしろ遅すぎると思っているくらいです。
ただ、この「歴史総合」が「近現代に限定」されているということについては、あり得ないと思いました。
なぜなら、それは、「歴史」というものを否定しているようなものだからです。
近現代における現象の理解のためには、過去の歴史の理解が絶対的に必要となります。過去の歴史の理解なしに、近現代の現象のみを学ぶということは、極端に言えば、テレビのニュースをそのまま頭の中に入れることと同じことだと思います。
つまり、歴史の学習というのは、世界の過去から現代にいたるまでの物語を理解することに他ならないわけです。ですから、この点については、「中央教育審議会」には是非再考していただきたいと強く思います。
また、英語をツールとして活用することを、実践することで生徒に教えなければならない英語の教師についても同じことが言えますが、このような大きな変更を加えるということには、それを教える教師の側にも大きな成長が求められることを忘れてはいけません。
「世界史」と「日本史」を融合するのであれば、世界と日本の関連性という視点でものを見ていく必要があります。
そうなると、もはや今までの暗記中心の受験というものを意識して授業を進めることなどありえないですし、今まで受験を前提に教えてきた教師の皆さんの考え方も従来のままでは、物語の理解からは遠く離れてしまうはずです。
新聞記事には、「今まで日本史を専門に教えてきた先生、世界史を専門に教えてきた先生が、それぞれの専門に偏って指導すれば、歴史総合の趣旨は骨抜きになってしまう」というような懸念がありましたが、この問題は、学校の教師に対して、考え方の転換を迫っていると思います。
どの分野でも、立ち止まり続けて何とかやり過ごせるような仕事はなくなったと捉えるべきですし、またその姿を生徒に見せるということがこれからの教師に求められることなのだと改めて感じました。