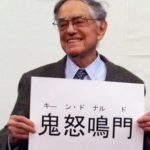言語的多様性モデルとしての日・米・欧
2020年9月2日 CATEGORY - 日本人と英語
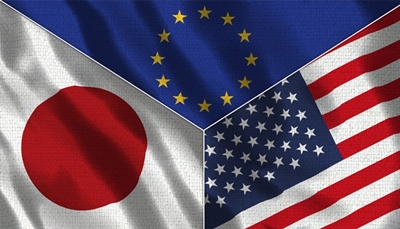
書籍紹介ブログにてご紹介した「共通語の世界史」からテーマをいただいて書いてきましたが、第六回目の今回が最終回です。
今回のテーマを「言語的多様性モデル」として、そのありようをアメリカとヨーロッパと日本という典型的な三つの場所を取り上げてまとめてみたいと思います。
前回の記事では、「言語的多様性モデル」としてヨーロッパモデルと日本モデルのという全く異なる二つのモデルを紹介しました。
まずは、「ヨーロッパモデル」です。
ヨーロッパは長い間言語に深く根差した文化的特徴を基に自分たちのアイデンティティを形成する場所として存在してきました。
その中で、言語の「多様性」と「統一性」という二つの相反する事象に対して真剣に向き合わなければならない歴史を経てきたことで、「否が応でも」そうせざるを得なかったことからこのモデルが出来上がったというものです。
一方で「日本モデル」です。
日本は、完全なる島国という地理的条件の下、歴史の早い段階で地理的に近い中国という先進国の言語・文化を取り入れました。
その後、長い時間それ以外の言語・文化を取り入れる必要性を感じず、むしろ排除する必要性を感じて中国の言語・文化の影響を強く受けた独自の日本語・文化を維持し続けました。
近代になってようやく、西洋の言語・文化を取り入れる必要性を強烈に感じたことから、英語を中心とした西洋文化を取り入れることになりました。
この日本の流れの中で注視すべきは、その外国言語・文化を取り入れる時の姿勢はあくまでも「自ら進んで」、そして「強い好奇心をもって」というものです。
これはヨーロッパが、「否が応でも」そうせざるを得なかったのとは対照的です。
したがって、この日本モデルのキモは、まず母国語である「日本語」を圧倒的な基盤としながらも多様性を「尊重」するという姿勢です。
最後に「アメリカモデル」ですが、これは実際には「言語的多様性モデル」ではなく、反面教師としての「言語的画一性モデル」と呼ぶべきものです。
本書では以下のように大変厳しい評価をしています。
「アメリカ合衆国はヨーロッパと異なり、新天地にやってきた移民たちが自分たちの出自の多様さを乗り越えるために、ただ一つの言語を結束の柱にしたような場所である。こんにちアメリカ合衆国では、他者の要求に耳を貸さない閉鎖性が一因となって英語への排他的な執着が引き起こす単一言語主義が深刻な脅威になっている。ヨーロッパ人はこうした危険から逃れなければならない。多言語の地の市民として、自らの言語を話す他者に対して関心を持つことがいつの日か、このようなアメリカによる言語の多様性に対する脅威から、世界に救いをもたらすかもしれない。」
このような救いようのなさそうな「閉鎖性」を持つアメリカに対してこのことの危険性を自覚させるためには、多言語の地としての「ヨーロッパモデル」を用いることが現実的ではなく、単一言語の地ではあっても他者への強い好奇心をもつ「日本モデル」を用いることのみが、いくらかの救いとなると信じるしか、他に手立てはないように思われます。