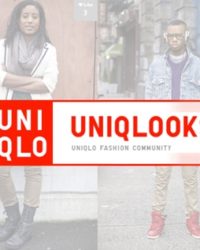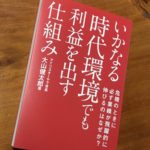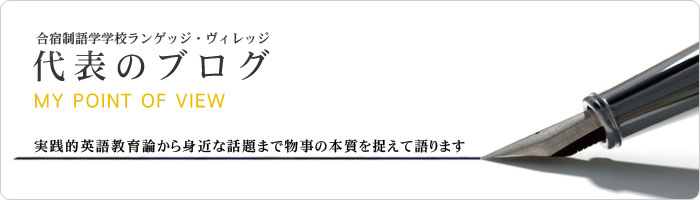
「甘え」の構造
2023年5月25日 CATEGORY - 代表ブログ
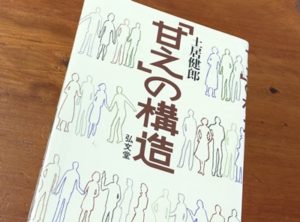
皆さん、こんにちは。
前回の「国民の底意地の悪さが日本経済低迷の元凶」の記事の中で私は以下のような感想を書きました。
「『他人の足を引っ張る日本人の特性が組織の秩序をもたらす』という部分に納得している自分を認識して、自分が日本人であるという事実に対してどうしようもなく恐ろしい気持ちになってしまいました。」
このことは、一人一人の「底意地の悪さ」が、それぞれお互いをけん制し合うことで全体としてまとまり(秩序)をもつということを意味しているわけで、本書はこのことを「甘え」という切り口で分析していたのが印象的でした。
そこで、参考文献として挙げられていた土井健郎氏の「甘えの構造」を読みましたので今回ご紹介します。
そもそも、「甘える」という言葉自体は日本語独特の表現だと私も今までの英語学習経験で分かっていたことです。
実際に辞書で調べると「depend on」「accept someone’s offer」「presume」などの語彙が出てきますが、これでは日本語の「甘える」のニュアンスを表現したことにはならないのは明らかです。
本書では、この「甘える」のみならず、「甘える」が成就しなかった結果の行動である「すねる」「ひがむ」「うらむ」など、これまた日本語独特の語彙を見つめなおすことで、日本人の心理の特異性を明らかにしています。
その際、著者がこの「甘え」という概念を「受身的愛情希求」という説明的表現で言い換えていたことに私は非常に説得的だと感じました。
また、日ごろ「甘え」(受身)に慣れているため、いったん甘えられないとなると、それを受け入れてくれない相手を「責める」という心の動きにつながり、「すねる」「ひがむ」「うらむ」などの動作につながっていくようです。
つまり、「自ら行動しないこと」を責めるのではなく「察しないこと」を責める精神性です。
「底意地の悪さ」であっても「自分を愛してほしい気持ち」であっても、それを能動的に相手にぶつけるというよりも、あくまでも自分の手を直接汚さず(労さず)に受身的にそれを実現しようとする感情が日本人の個々人、そしてそれが全体として働くということをこの言い換えで理解することができました。
(ただし、著者はこの「甘え」の感情は本来は日本人に限らず人類の本能に基づく普遍的なものであるが、欧米社会がそれを締め出しているために、結果的に日本において特に発達し、神と個人との契約を重視するキリスト教の影響の強い欧米においては発達しなかったものだとしています。)
そして、面白いのは、著者がこのことが実は日本人を個としては弱いが、集団としては個としては持ちえない力を発揮し強くなるというように、好意的に評価しているところです。
これについては、著者がこの本を書いた時期が1970年代という日本の高度経済成長期であったことと無縁ではないと思われます。
それから半世紀が過ぎた日本の現状を鑑みるに、日本の「甘え」の構造に対する著者の好意的な評価をそのまま引き継ぐのは難しいというのが大方の日本人の正直な感想ではないでしょうか。