
科学者という仕事
2019年9月15日 CATEGORY - 代表ブログ
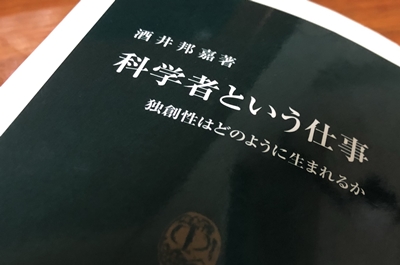
皆さん、こんにちは。
前回まで四回にわたって、書籍紹介ブログにてご紹介した「チョムスキーと言語脳科学」に関する記事を書いてきました。
その中で、最も印象的だったのは、今まで人文科学の分野という前提で研究されてきた「言語学」をチョムスキーが自然科学の分野として捉えなおしたことによって、その研究姿勢が非常に厳しいものに変わったと感じた点でした。
そこでは、一つの対象の研究を「自然科学」として扱うということは、「客観性(証明ができること)」「普遍性(広い対象に当てはまること)」「再現性(繰り返し起こること)」の三つの基本を踏まえるという厳しい選択をすることであるということを学びました。
同時に、人間の心のような非常に変数の多いものを研究対象とする場合には、最初からそれらを踏まえることを諦め、「博物学」すなわち蝶々集め的な姿勢に甘んじなければならず、チョムスキーのように従来そのような分野と思われていたところに、この厳しい姿勢を持ち込もうとすることがどれだけ挑戦的なことかということも学びました。
その上で私は、チャキチャキの文系人間ではありますが、そのような気の遠くなるような姿勢を貫く「科学者」の本質をもう少し深く知りたいと思いました。
この本の著者である酒井邦嘉氏は、もともと物理学を学ばれた科学者であり、そのチョムスキーの偉大な決断を後進として支えている一人です。
その著者が、そのものズバリ「科学者という仕事」という本を書かれていましたので、さっそく読んでみることにしました。
読んでみて感じたことはやはり、「科学者」という生き方の厳しさでした。(笑)
まず、科学者となるためには、小学校、中学校、高等学校、という少なくとも12年間という知識の積み上げが必要となります。ここの部分については、制度として通るかどうかは別として、必ず通らなければならない部分です。もちろん、やれ数学が苦手だの、物理が嫌いだのという言い訳なしにです。
つまり、この時間が最低限の「下積み」にあたります。
そして、大学(学部)という場所で初めて、「研究」という活動に入ります。しかし、ここはあくまでも「模倣」の段階です。先人に習って、研究の仕方や考え方を確実に真似ます。
ただ、真似る中でも、その中で主体的に「考える」姿勢は持たなければなりません。受身での模倣は、オウムが真似ることと同じであり、その内容をよく吸収できないからです。知恵を働かせながら、模倣をすることで次の段階につながります。
次は、大学院です。この段階でようやく「創造」の段階へ移行します。
ここまでくると、その分野において、何が分かっていて、何が分かっていないかが明らかになってきます。その認識の上で、自分の力で何か新しい研究をするという段階です。
この流れに沿って、一人の「科学者」が出来上がり、その一人一人が、独創性をもちながら「客観性(証明ができること)」「普遍性(広い対象に当てはまること)」「再現性(繰り返し起こること)」の三つの基本に則りながら、研究を進めていく、それによって全体として、人類の「自然科学」は発展してきたと言えます。
このことに関して、本書における次の言葉が文系人間の私の胸にグサッと刺さりました。
「理系のカリキュラムでは、実験のトレーニングや、理論的な問題を解く演習がかなりの時間を占めている。それでは、文系の環境で育った人が、一念発起して科学研究を目指すことはできるだろうか。高校から大学院まで、10年以上もの長い期間をかけて行われる科学専門教育の『下積み』の過程を、短期間で一気にクリアする方法があるのなら、とっくに採用されているはずである。文系の人が理系に移るためには、それだけの時間と覚悟が必要だ。このことは、朝永振一郎の次の言葉によく表れている。『私の自然科学研究の経験は、すべてのことに近道のないことを教える。一つ一つの積み重ねをたゆまず、あきることなくやっていく、それが最も確実な方法であり、それが最も速やかに目的に達する道であると私は信じている。』」
逆に、人文科学の分野はこのような「厳しさ」を積み上げてきたでしょうか。
自分自身のアカデミックヒストリーを振り返り、また周りを見渡しても、個々の事例は別にして、分野全体ではとてもそうだとは言えない気がします。
だからこそ、ノーム・チョムスキーの「言語学」の「自然科学」化は、革新的なことだと言われるのだと思います。
言語学に限らず、人文科学の分野全体として、もう少しこの点を見つめなおす必要があるような気がしました。
















