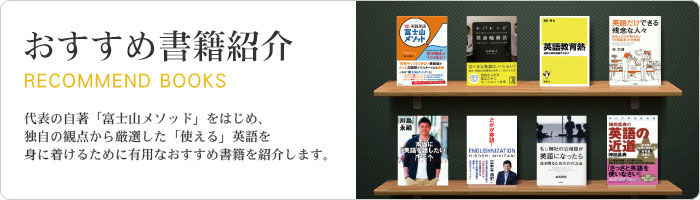
英語支配とことばの平等 #104
2015年3月19日 CATEGORY - おすすめ書籍紹介
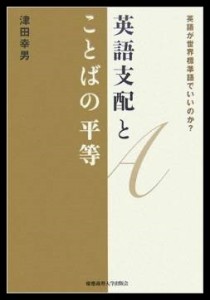
【書籍名】 英語支配とことばの平等
【著者】 津田 幸男
【出版社】 慶應義塾大学出版会
【価格】 ¥2,400 + 税
【購入】 こちら
#102でご紹介した「英語支配の構造」の続編といえるものです。
確かに、私自身も、日本にいる外国人から街中で道を尋ねられるときにいきなり英語で話しかけられると「むっ」としますし、礼儀としてその国の人に対して一言目はその国の言葉で話しかけるという気遣いくらいはすべきだと思います。
ですので、私としても英語支配や英語帝国主義という考えに対して、なんらかの対処は必要かなとは思いますし、このブログにも「英語帝国主義」についての記事を書いています。
しかし、前著「英語支配の構造」は、英語支配に対する批判に終始していた感がありました。
私は、外国語の教授を自らのビジネスとしていますので、グローバリゼーションという動きをポジティブに考えていますし、日本人が英語を使えるようになることは、日本人の生活を向上させる上で必要不可欠であるという考えが、大前提であると思っています。
ただし、その前提以前の問題として、日本人が日本語や日本文化を自らのアイデンティティとして大切にすることは当たり前の話です。その当たり前の話に対する「なんらかの対処」の必要性という視点から期待しながら本書を読み始めました。
残念ながら、本書にあげられていた「英語支配」への対処法はあまりにお粗末といわざるを得ませんでした。
著者があげていたのは以下の三つです。
日本における英語使用に課税する「英語税」の導入、英語支配に対する罪滅ぼしとしての「英語教育無償化」を実現するための負担の義務化、それから、言語の平等を実現するための「外国語使用の義務化」(外国人に対して発信する場合、自国語を使用してはいけない)です。
あまりに、荒唐無稽で自己中心的な被害者意識に終始した発想であり、この「英語支配」という問題自体の重要性を逆に下げてしまうような気さえしました。
毎回言っていることですが、日本語で考えることで日本人として世界との差別化を最大限にはかり、世界に対して英語を利用して発信することで、その大きな市場を最大限に活用することが重要なのです。
ですから、グローバル化からはどうしても逃れることはできない以上、自らの言葉と文化に立脚したアイデンティティをどう維持、発展させるかはその言葉を有している我々マイノリティの側の責任であって、決してマジョリティーに責任転嫁するべきではないと思っています。
文責:代表 秋山昌広
















