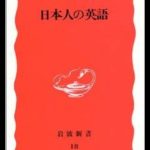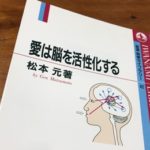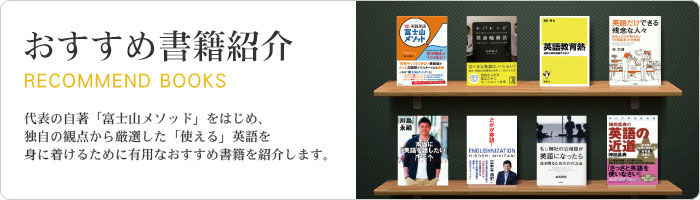
「グローバル人材育成」の英語教育を問う #161
2017年4月20日 CATEGORY - おすすめ書籍紹介
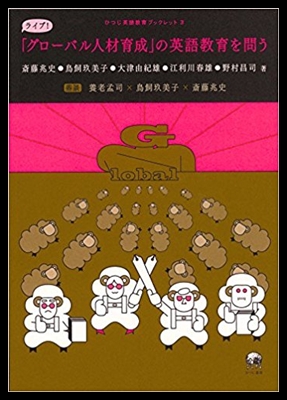
【書籍名】 「グローバル人材育成」の英語教育を問う
【著者】 斎藤兆史・鳥飼玖美子・大津由紀雄・江利川春雄・野村昌司
【出版社】 ひつじ書房
【価格】 ¥1,200 + 税
【購入】 こちら
私が尊敬する英語教育界の4人の侍(鳥飼先生は女性ですが)が日本の英語教育の改悪に待ったをかけるために共同で出版された#26「英語教育、迫り来る破綻」と#66「学校英語教育は何のため?」に続く第三弾です。
今回は、その4名に加えて、もう一人若手の研究者である野村昌司中京大学准教授もコーディネーターとして加わってらっしゃいます。
本書の冒頭において、その野村准教授が、日本の英語教育の問題を議論する前提として最も根本的なことの確認を行った上で議論を進めており、非常に議論が明確になっています。
それは、「国際化」の概念と「グローバル化」の概念の違いについてです。
恥ずかしながら、私としてもこれを混同していた感が否めません。
まず、「国際化」とは、「国の枠組みを前提として複数の国家が相互に交流し、互いに経済的・文化的に影響を与え合うこと」、そして「グローバル化」とは、「国歌の枠組みと国家間の壁を取り払い、政治、経済、文化など、様々な側面において地球規模で資本や情報のやり取りが行われること」です。
前者は、お互いの違いを尊重し、違う者同士が相互に影響を及ぼしあうことを前提しているのに対して、後者は一つの価値観、一つのルールによって統一を図ることを前提としています。
つまり、似て非なるもの、いやむしろ全く正反対の概念だと考える必要がありそうです。
その理解で行くと、現代は前者ではなく、明らかに後者、しかも「英語圏」の価値観を唯一のルールとする「グローバル化」に他ならないわけです。
このことを前提に、英語を母国語としない私たち日本人の教育をどのようにするのかということを考えていかなければならないわけですが、この二つの違いを理解しないままに教育の議論が進んでいくことで政策が歪められていることが本書において明らかにされています。
前作、前々作も非常に鋭い視点での議論がなされていましたが、本作も問題の核心を突く素晴らしい内容でした。
文責:代表 秋山昌広