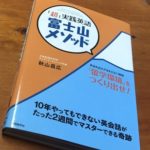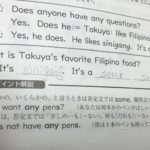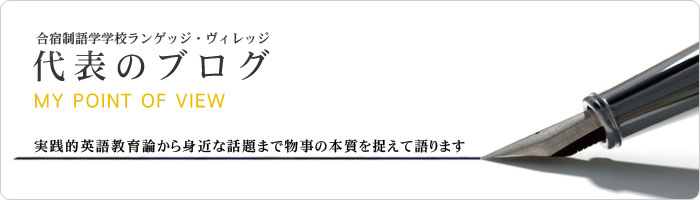
精神の不老不死
2016年6月26日 CATEGORY - 代表ブログ

皆さん、こんにちは。
前回の「不老不死」記事にて以下のように書きました。
「一人ひとりの人間の単位では、平均寿命という枠の中で春夏秋冬のごとく人生を全うしようと言う目標ができるわけで、この枠を取っ払ってしまった先には何を目的にしていいかと言う途方もない大きな課題が突きつけられるはずです。」
ここでは、平均寿命という枠で考えていますが、それよりもずっと短いスパンの中で人生を全うしようとした人として吉田松陰がいます。今回、彼についての「感化する力」という本を読んでこのことについてより深く考えさせられました。
吉田松陰は、江戸幕府末期において、日本の欧米による植民地化を回避するためには、幕府の対応では不十分で、幕府や諸藩の別に関係なく日本を強い国に作り変えなければならないということを主張していました。
彼のすごいところは、主張するにとどまらないことです。松下村塾の塾生に対しても、幕府に対しても直情型で本音をぶつけていきます。そして、その行動はとどまることを知らず、幕府の幹部の暗殺計画にまで及び、遂には幕府によって死罪を言い渡されるまで続けます。
この際、彼は自らの人生における春夏秋冬をまさにこの時の自分の年齢である29年間の中に収めようと決心し、その通りに死に急ぎました。この時の彼の心情を筆者は以下のように代弁しています。
「仮にどれだけ長生きしても、日本を強い国に作り変えるということを完成させることは難しい。ならば、一人生きながらえて進捗を見守るよりも、自分の思いを受け継ぐものを育て、何代か先でも結実してくれることを願う方が合理的だ。」
この心情は、この有名な辞世の句に詠まれています。
「身はたとひ武蔵野の野辺に朽ちぬとも留めおかまし大和魂」
実際に、江戸幕府を倒し、明治政府を作った中心人物の多くに松下村塾の塾生が多くいたということは、まさに、春夏秋冬のごとく人間がやるべきことをやって、死を迎え、その遺伝子や志を次の世代につなげていくということはそれ自体が幸せなことだということを証明していると言えるのかもしれません。
人間にとっては、肉体の不老不死は本質ではなく、精神の不老不死が本質的価値なのではないでしょうか。